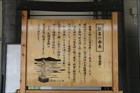Page:4 ※各画像はクリックすると拡大します。 |
||||||||||||||
  
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
こまち3号を田沢湖で下車しました[①]。名前の通り、観光名所でもある田沢湖への最寄り駅で、今回私がここで下車したのも、田沢湖で観光をするためです。以前は生保内(おぼない)という駅名を名乗っていました。 改札を出てふと発車標を見てみると、そこには、上下ともこまち号の表示しかありませんでした[②]。このときは、「なるほど、こまち号専用の発車案内があるわけだな」と考えたのですが、後になって、この時間帯(日中)は、本当にこまち号の発着しかないことを知りました。田沢湖を出る定期の普通列車(平日)は、下りは6本で、上りに至っては4本しかないという、まるで北海道の駅のような列車構成です。 最速記録を生み出すために停車駅を絞った1往復以外の全てのこまち号が停車する田沢湖駅ですが、街自体はさほど大きなものではなく、ここにこまち号が停まるのは、あくまでも観光のための要素が強いと言えます[③]。旅の計画当初は、「どうせなら車で田沢湖を一周してみようか」と考え、レンタカーを借りるという選択肢もあったのですが、「借りる時間が短すぎてもったいない」との理由で却下しました[④]。 そういうわけで、田沢湖へはバスで向かうことにします[⑤]。駅を10:40に発車する田沢湖方面への路線バスがあるため、それに乗車して田沢湖へ向かいます。どうにもバスと列車の時刻が合わないというのであれば、それこそ多少もったいなくてもレンタカーを借りていたかもしれませんが、ありがたいことに、行きも帰りも、ちょうど良い待ち時間で列車とバスが接続してくれています。 このころ、関東では、まだまだ紅葉は始まっていませんでしたが、北東北では紅葉が見ごろを迎えていて、バスの車内からも、適度に色づいた木々を随時見ることができました[⑥]。これまでは、秋に遠出の旅ができる時間などなく、それに伴い、旅先で紅葉を楽しんだこともなかったのですが、大学4年生特有のスカスカな時間割のおかげで今回は旅に出ることができ、史上初めて本格的に紅葉も楽しむ旅となっています[⑦]。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
  
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
路線バスを「田沢湖畔」バス停で下車し、すぐ近くにある窓口で乗船券(1100円)を購入。これから田沢湖遊覧船に乗船します[①]。 明日以降は祝日を含む3連休となるため、田沢湖にも多くの観光客が訪れることでしょうが、今日は平日なので、遊覧船に乗る人もあまりいませんでした[②]。座席に座りながらまったりとクルージング・・・といきたいところでしたが、元々そのような仕様なのか、あるいは経年劣化なのか、遊覧船の窓は色付き状態と化していて、窓越しに景色を見るとこんなことに[③]。しかも固定窓で、窓を開けることもできません。 そんなわけで、私は、出航後すぐに後方のデッキに出て、そこで大半の時間を過ごしましたが、そこから、私はいくつもの絶景に出会いました。 1本1本異なる色合いで色づいた木々は、1日として同じ眺めにならない刹那の風景を織り成し[④]、遊覧船が進むその軌道は、風もなく穏やかな水面に、水だけで作られる”芸術”を生み出します[⑤]。また、まるで絵の具を溶かしたかのような、単なる「青色」には収まらない独特な水の色は、田沢湖の象徴的な光景です[⑥]。そして御座石神社の鳥居が水鏡を作れば、その場はたちまち神秘的に・・・[⑦]。 白浜(出発時の拠点)のほぼ対岸には、「たつこ像」と呼ばれる金色の像があり、田沢湖の代表的な観光スポットとなっています[⑧]。かつての伝説に基づいて建立した像とのことですが、大仏などとは異なり、近代になってから人工的に作られたものであり、また、悪趣味と紙一重な全身金色という出で立ちも相まって、一部にはよく知られた「がっかりスポット」。まあ、たしかに、期待して出向くと・・・かもしれません[⑨]。 この上なく美しい色合いで、そして神秘的な雰囲気を漂わせる田沢湖の湖水ですが、たつこ像付近で船が停止しているときに水面に目をやると、小さな魚たちが湖中を縦横無尽に駆け巡っていました[⑩]。しかし、その眺めは、「魚が湖(ないしは海、川)を泳いでいる」というよりかは、「魚が青空を飛んでいる」という表現の方が合うような気さえしてしまいます。本当にここが湖とは思えないほどです。 40分ほどの所要時間で遊覧は終了し、出発時の拠点に戻ってきました[⑫]。この看板につられて・・・というわけではありませんが、時間帯も時間帯で、また帰りのバスに乗るまでにはまだ時間があるため、このあと、レストハウスに立ち寄って昼食を食べる予定です。 湖の淵は水深が浅く、先ほどのような青色とはなっていませんが、その代わり、船乗り場へと至る通路のあたりを中心に、多くの小魚たちが元気に泳いでいます[⑬]。そして、田沢湖も商売上手なもので、1袋100円で「魚の餌」を販売しており、この魚たちに餌をやることもできます。餌を購入した初老の男性から、「餌やりします?」と餌を分けていただくことができ、2人で同時に餌を投げると・・・、この食いつきぶり![⑭] |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
  
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
帰りのバスがやってくるまでの待ち時間を利用して、レストハウスで昼食を食べることにしました[①]。牛丼セット(910円)とアイスコーヒー(380円)を注文し、ここでのんびりと昼食タイム。その合計金額は1290円となりました。私は、旅費を概算するときは、食事代は1食1000円に設定しているのですが、そういえば、最近は1000円で収まることの方が少なくなってきたような気もします。そろそろ見直しますかね。 そしてバスに乗車して田沢湖駅に帰ってきました[③]。ガラス張りの駅舎は、今となっては特段珍しいものではありませんが、田沢湖駅の駅舎は、写真のように、側面は全面ガラス張りで仕立てられている一方で、屋根等には木材がふんだんに使われていて、ガラスと木がハイブリッドになっている、他にはあまり例がないと思われる造りになっています。 次に乗車するのは、13:11発のこまち13号です[④]。発車標は3段分のスペースを持っていますが、やはりこまち号の表示しかありません。ただ、15:11発のこまち19号の後には、15:37発の大曲行きの普通列車があるため、こまち13号が発車すれば、ここに久しぶりに普通列車の表示が現れることになります。もっとも、私はそれを目撃することはできないわけですが。 東京〜秋田間を結ぶこまち号が多数往来しているため、あまりそのような印象は抱かれていないかもしれませんが、田沢湖を発着する普通列車のあまりの少なさからも分かるように、田沢湖線は本来はローカル線で、実際に地方交通線にも指定されています。しかし、一方で、全通は1966年と比較的遅いものでした[⑤]。全線開業からはまだ50年程度しか経っていません。 ここは紛れもなく在来線の駅ですが、新在直通車両のE6系がやってきているように、線路は標準軌となっています[⑥]。北海道新幹線の青函トンネル区間などとは異なり、狭軌と標準軌が併存する「三線軌条」とするのではなく、狭軌を標準軌に改軌してしまいました。 先ほどのこまち3号では普通車に乗車しましたが、今度はグリーン車に乗車します。11号車のところで列車を待ちましょう[⑦]。 |
||||||||||||||
TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |