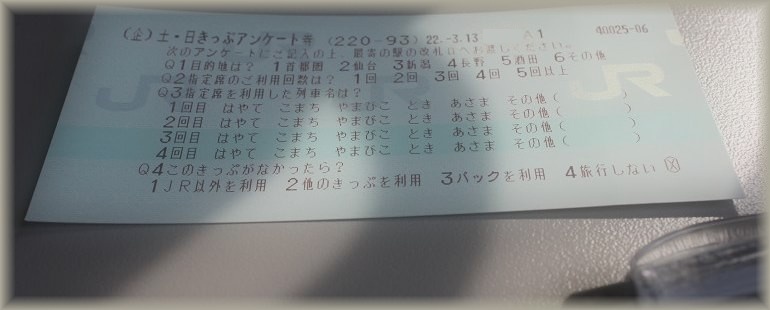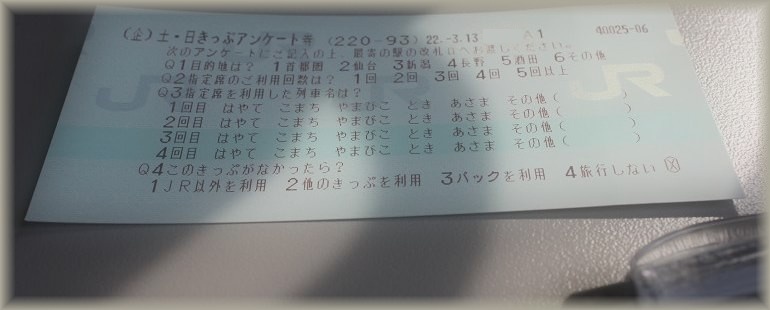|
次に乗車する列車は、10時53分発の、野辺山行きの八ヶ岳高原列車3号。
土曜・休日にのみ運転される臨時列車で、各駅停車の普通列車ですが、列車名があります。
・・・で、これは5番線からの発車で車両はキハ110系なのですが、4番線にも同じキハ110系の11時20分発の列車(定期)が停車していて、どっちが何なのか正直、ぱっと見では分かりませんでした。
幸い、方向幕を見て、5番線のキハ110系に「臨時」と表示されていたので、まぁこっちが八ヶ岳高原列車3号なのだろうというのは一応分かりましたが・・・。
小淵沢駅は駅舎内だけでなく、ホームにも発車標がありません。
このとき、初めて発車標のありがたみをしみじみと感じました。
|
 小海線8253D 八ヶ岳高原列車3号(キハ110系)
小海線8253D 八ヶ岳高原列車3号(キハ110系)

小淵沢(10:53)〜野辺山(11:25)
|
 |
10時53分、定時で列車は小淵沢駅を発車。
普通列車ながら、「八ヶ岳高原列車」という列車名がご丁寧にも付けられているので、車内放送も列車名入りのものを期待しましたが、ごく普通の「野辺山行き、ワンマン列車です」という味気ない放送・・・。
小淵沢駅を発車すると、すぐに知る人ぞ知る、180度向きが変わる「小淵沢の大曲」を走ります。
列車内から窓越しに見てもこれだけ曲がっているのが分かるのですから、いかにこの大曲の曲がり方が、尋常でないかということをお分かりいただけることかと思います。
|
 |
小淵沢駅から8分で、甲斐小泉駅に停車。
「八ヶ岳高原列車」という列車名と、野辺山行きという行き先、そして臨時列車であることから推察できますが、この列車はJR線の駅では最も高い標高に位置する、野辺山駅へのアクセス列車の色合いが強いです。
しかし、小淵沢〜野辺山間無停車だったりするわけではなく、列車は終点の野辺山まで各駅停車。
地元の方々も、単純に普通列車の増発と見ているのか、最初の途中停車駅の甲斐小泉駅でも、早速この列車から下車していく人の姿が見られました。
|
 |
小淵沢の大曲をつい先ほど通ったばかりですが、小海線の線路は、右へ左へ山間部を縫うように敷かれており、蛇行を繰り返します。(←も右へ曲がった後、また左へ曲がっています)
そのため列車も大して速度を出さず、のんびりと走ります。
今ひとつの線形の線路を、ゆっくりと列車が走る。これこそ、ローカル線の醍醐味と思います。
|
 |
11時17分、清里駅に到着。
清里駅は、小海線の駅にあっては、野辺山駅の次に標高が高い駅となっています。(1274.6m)
上りホームの隣では、C56形が静態保存されていました。
C56形は、全国に20両が静態保存されているそうで、それとは別に2両が動態保存されています。
|
 |
時折、線路脇にこのような簡易な階段があるのを目にしました。
走っているところが走っているところで山間部なものですから、保線などのために線路に入ることが一苦労なのは容易に想像がつきます。そして実際、このように森林の中から線路脇に階段がのびてきています。
車で来て森林の外の道に止めて、木々の間を抜けて階段へ。
そしてこの長〜い階段を上って線路に来て、さて保線開始・・・、という流れなのでしょうかね?
|
 |
終点の野辺山駅の手前では、巨大なパラボラアンテナを目にすることができます。その直径、なんと45m。
これは国立天文台のものだそうで、天体からの微弱な電波を捉えるためのものだとか。
自動放送でしたが、このパラボラアンテナについての簡単な紹介も放送されました。
|
 |
小淵沢駅から32分、11時25分に終点の野辺山駅に到着。
一応「JR最高標高の駅(1345m)」なのですが、空気が薄い気がするとか、耳が痛いとか、そういったものがないので、いまいち「高いところにいる」という実感がわきません・・・。
まぁ、ゆっくり上がってきたから感じないだけなのかもしれないですけれどもね。
|
 |
しかし、この「証明」がある以上、野辺山駅は紛れもなくJR線最高標高の駅です。
JR線に無数にある駅の中で、ここ野辺山駅が標高において「1位」
何のことで1位なのか、ということはさておいても、ウン千とある中で1番というのは、やはりその駅にとっての誇りになるというか、大きな特徴付けができると思います。
|
 |
駅名標。こちらには「最高〜」とか「標高〜」などという表記は特になし。
|
 |
キハ110系を改めて撮影。
このときに気が付いたのですが、正面左上に書かれている車両番号が「110−110」ということで、車両形式と製造番号が一致していました。
個人的には、ある車両のトップナンバー車に乗ることができるのよりも、形式と製造番号の数字が一緒の車両に乗ることができる方が嬉しいですね。
|
 |
列車は方向幕の表示を変えて、折り返しの準備を済ませていました。
ワンマン小淵沢行き、こちらも先ほどまで乗車してきた八ヶ岳高原列車で、上りの4号になります。
八ヶ岳高原列車は、合計4往復が設定されており、上りの最終の8号は野辺山14時48分発です。
|
 |
駅員に土・日きっぷを見せて改札を抜けて、まず目についたのはストーブ。
厚着をしてこなかった私でも、正直、このときは寒いとは思いませんでしたが、ストーブには火が入っており、近づくとなかなか暖かかったです。
冬には、このストーブが大活躍するのでしょうね。
|
 |
JR線最高標高の駅にふさわしく(?)、駅舎はなかなか凝ったデザインのものでした。
どこか「協会」と思わせるような感じ。
画像には映っていませんが、駅のすぐそばに観光案内所があり、そこでは自転車の貸し出しも行われています。
時間があれば、野辺山駅を訪れたついでに自転車を借りてみて、JR線最高標高の駅の周辺を走り、爽やかな高原の空気を体いっぱいに浴びてみてはいかがでしょうか?
|
 |
日陰には、まだ雪が残っていましたが、これが結構固まっていて、上を歩いてみるとまぁずいぶん滑ること。
もちろんほとんどの人はここを避けて歩くので、周りの方々からしたら、あえて雪の上を歩いている私は、どうみても特異な存在ですな(笑)
|