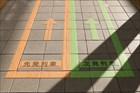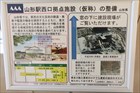Page:102 ※各画像はクリックすると拡大します。 |
||||||||||||||
  
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
なんとなく、「これは岩見沢駅です」と言われてもおかしくはないような気がする、そんな新庄駅構内[①]。とにかく、その雪の量には、ただただ圧倒されるばかりです。なお、このときの新庄市の積雪は、151cmでした。 いま乗車してきた列車は、酒田行きの普通列車として折り返します[②]。陸羽西線の列車には、余目止まりのものもあり、全てが酒田まで乗り入れるわけではありません。まあ、酒田の隣で分岐しているわけではないですからね・・・。 ホームから線路まで、一面が雪にまみれていた新庄駅構内とは打って変わって、駅前は、除雪がよく行き届いていました[③]。ロードヒーティングが仕込まれているのか、道路は、非降雪地帯と比べても遜色がないくらいで、アスファルトも乾いていました。現在は気温も上がってきていて、多くの場所で、積もった雪が融け出していました[④]。 現在の駅舎は、1999年の奥羽本線山形〜新庄間の改軌(いわゆる山形新幹線の開業)に先駆けて、1998年に完成したものです[⑤] [⑥]。山形新幹線を本当の新幹線とみなすのかどうか・・・はともかくとしても、街の玄関口となる駅が、東京と一本で結ばれているというのは、大きな意味を持ちます。ま、個人的には、別に在来線特急→福島(仙台)乗り換えでもいいのでは、と思いますが。 「自主規制」との一文が添えられた進入禁止の標識[⑧]。これは、山形県においては、さほど珍しいものではなく、”公安委員会が公式に設置した標識ではなく、自治体や地域住民が自主的に設置した標識”であることを意味しています。たまに「止まる」という道路標示を見かけるかと思いますが、あれも、「本当の止まれはないが、止めさせたい」というときに、自治体等が自主的に書いているものです。 自然に任せ、なすがままに雪を積もらせていくとどうなるのか。その答えがこれです[⑨]。この雪の下に何があったのか、もはや分からなくなってしまっていますが、人が手を出したら生み出せないような曲線美、複雑さ、柔らかさ、しなやかさ・・・は、まさに「自然の造形美」と言えます。私は知っています。いま、ここに手を突っ込んでみたら、そのふわふわとした感触に驚くことを! 駅舎内の様子[⑩] [⑪]。一応、”新幹線の駅”ではありますが、自動改札機は、まだ導入されていません。現在、フル規格の新幹線の駅では、有人改札が残っている駅(新幹線の改札口に限る)は、もはや全滅しています。新幹線の1日の乗車人員が100人にも満たないような駅であっても、自動改札機が導入されています。 新庄市への来訪を歓迎する看板[⑬]。そのつばさ号の写真は、旧塗装時代のE3系2000番代です。もはや振り切って初代の400系とか、新しい塗装のE3系とかであれば、何もおかしいことはありませんが、旧塗装時代のE3系2000番代とは、これまた中途半端な。E3系2000番代は2008年12月に導入され、現在の塗装は2014年4月に登場したので、その間に撮影・作成したものということになります。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
  
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
つばさ150号に乗車します[①]。それにしても、つばさ号のこの新しい塗装、賛否両論色々とあるようですが、個人的には、運転室横〜前照灯横にかけての「白い部分」の存在意義がよく分かりません。ここも紫色に塗り上げておけば、そこまでおかしな塗装ではなくなるように思うのですが、これがあるせいで、どうも・・・。 この150号を逃してしまうと、次は17:12発の156号となり、2時間ほどの間隔が空きます[②]。新庄発着のつばさ号は、基本的に2時間に1本であり、1時間に1本(時間帯によっては2本)はある山形駅と比較すると、幾分不便であることは否めません。まあ、数は少なかろうとも、東京に直通する列車があるということが、山形〜新庄間の各駅にとっては、とても大きな意味を持っているわけですが。 ここは在来線の駅なので、各乗降扉の下側に備えられている「ステップ」は格納されています[③]。フル規格の新幹線駅に停車する際は、これを跳ね上げて、ホームと列車との間に生ずる隙間を埋めてくれます。 山形まで普通車指定席に乗車します[④]。2列席であるのは、これがD席・E席だから・・・ではなく、もう皆さんもご存じのことかとは思いますが、E3系が在来線規格の大きさで設計されている車両だからです[⑤]。座席はA・B・C・Dによる4列配置で、車内空間も、フル規格の新幹線車両と比べると小さく、まさに在来線特急に乗っているような気分です。 新庄を飛び出したつばさ150号[⑥]。一面の銀世界を進んでいきます。積もりに積もった大雪は、時に、窓越しに見える景色の全てを覆い尽くしてしまうほどの高さを誇り、その視界を遮ります[⑦]。JR東日本の新幹線が「大雪で運休」というのは、まず聞きませんが、いわゆる山形新幹線は、雪害による運休もしばしば起こります。 いい加減、この手の景色をどう形容してやろうかと迷ってきてしまっているところ(もう何度も取り上げているので・・・)ですが、やはり雪景色というのは、非常に美しいものであると感じます[⑧]。もうすっかり見慣れた景色ではありますが、その一方で、少しずつ陽が傾いてきたことによって、雪原上に建物や吹き溜まりの影が伸びてきており、それがこの車窓にアクセントを加えています。 遠くに見えるこの山は・・・、何というものでしょうか[⑨]。川は、Google Mapでも見れば、すぐにその名前を特定することができるのですが、山については、それがちょっと難しいです。特に、そこに分かりやすいものがひとつドカンと鎮座しているのではなく、連山になっているような場合は・・・。山形県の内陸部は、平地の両側に山が聳えていて、どちらを見ても山となります。 下り列車との行き違いを行うために、漆山で運転停車[⑩]。かっこよく「山形新幹線」、「秋田新幹線」とは言ったものの、在来線区間においては、所詮は”在来線特急”。路線が単線であるならば、行き違いによる運転停車は、必ず起こりえます。例えフル規格の新幹線でもあっても、この先、極端に輸送量が少ない場所に敷設するならば、あるいは単線で建設されることもあったりして・・・。 まもなく山形です[⑪]。一見、複線になったように思われますが、よく見てみると、これが狭軌であることにお気づきになることかと思います。山形駅には、狭軌の在来線である左沢線と仙山線の列車が乗り入れてくるので、それらの列車のために、狭軌の線路が残されています。左沢線が北山形、仙山線が羽前千歳で分岐するので、そこまでは狭軌が用意されます。 下車駅の山形に着きました[⑫]。ここまでは、乗客はそれほど多いものではありませんでしたが、指定席・自由席共に、山形でぞろぞろと乗り込んでいきます。さすがにそこは県庁所在地、ということか。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
 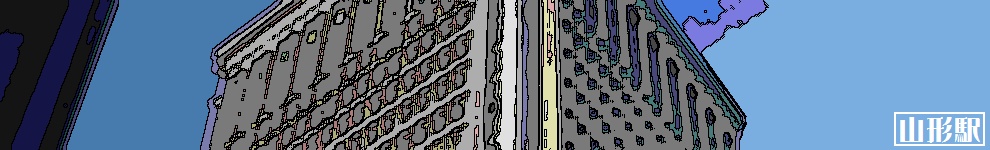 
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
山形駅のホームには、先発のつばさ号用の待機列と、次発のつばさ号用の待機列が用意されています[①]。つばさ号は、全車指定席ではないため、とりわけ繁忙期には、自由席がよく混雑します。なお、繁忙期には、単独の臨時つばさ号が走ることがありますが、そのような列車は、東京〜福島間でやまびこ号の輸送力を借りることができないので、全車指定席になることが多いです。 つばさ号を模した・・・と思われる、ダイヤブロックによる模型[③]。ただ、その色合いは、実際の車両とは、ちょっと異なるようです。あと、そもそも、ここはとれいゆつばさ号を宣伝している場所なのですから、とれいゆつばさ号をダイヤブロックで作れば良かったのでは?と思います。なぜ、普通のつばさ号なのか・・・(それも、色の再現度にだいぶ疑義のある一品)。 今回の旅では、各都道府県の代表駅において、そのスタンプを収集することにもしています[④]。というわけで、早速、スタンプ置き場にやってきたのですが・・・、なんと、修理中?[⑤] 近所の駅なら、後日回収に来るということは容易ですが、山形となると、そうはいきません。ただ、幸い、小さい方のスタンプは生きていたので、それを使いました。 東西を結ぶ自由通路[⑦]。幅は約15mほどがあるようで、とても広々としています。この自由通路を介して、雨に濡れることなく直接行くことができるビルが、霞城セントラルです[⑧]。飲食店やオフィスはもちろんのこと、宿泊施設や学校までもが入居した多目的複合ビルとなっていて、その高さは、地上約115m。これは、山形県内においては、最も高い建築物となっています[⑨]。 霞城セントラルの最上階は24階で、この一角には、山形の市街地を一望することができる展望室が設けられています[⑩]。入場は無料で、駅からもとても近い(しかも濡れない)ので、山形駅周辺のお手軽観光スポットとして、次の列車までの時間潰しなどにオススメです。この視点は東口側のものですが、こちらは、商業施設やマンションが集積していて、よく発展しています。 東口方面への視線を進めていくと、その先で巨大な山々にぶつかります[⑪]。いま、私は、事実上宮城県方面を眺めているのですが、このように、山形県と宮城県は、険しい山々によって分断されています。山形〜仙台間を結ぶ鉄道路線としては、仙山線がありますが、やはり県境を超える区間は、沿線人口も非常に少なく、線形も厳しくなります。 山形駅を上方から眺めた図[⑫]。駅舎に接続して、留置線と駐車場を跨ぐようにしながら、東西自由通路が伸びています。山形駅には、奥羽本線(山形新幹線)の標準軌と、左沢線・仙山線用の狭軌の両方が敷設されていることは、先ほども少し触れたことかと思いますが、異なる軌間の線路が混在していることは、上から見てもよく分かりますね。 ”裏手側”となる西口では、現在、再開発が行われていて、「複合文化施設」の建設が進められています[⑬] [⑭]。ところで、今は冬なので、当然に雪が降り、積もっていますが、基礎工事も建築工事も、特にどうということなく進んでいるのでしょうかね。まあ、「山形で建設工事」をやるからには、当然、雪に対する対策というのは、いろいろと打ってあるに違いないはずですが。 |
||||||||||||||
TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |