 Page:42 ※各画像はクリックすると拡大します。 |
|||||||||||||
 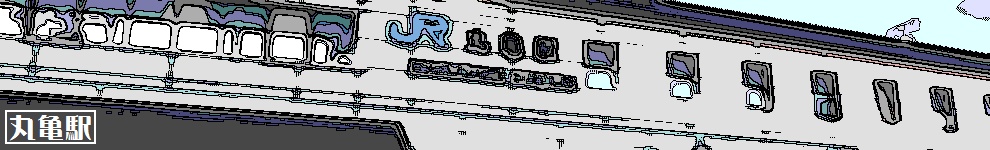 
|
|||||||||||||

|
|||||||||||||
丸亀で下車しました[①]。相対式2面2線の簡単な構造ではありますが、全面的に高架化されていて、また全ての定期列車が停車します[②]。琴平まで延長運転されるときのサンライズ瀬戸号が、唯一丸亀を通過するという体験ができる列車です。 2016年の登場以来、春・夏・冬の長期休暇時に決まって発売されるようになり、今やすっかりおなじみとなった「若者限定四国フリーきっぷ」[③]。今回は使用可能時期が合わなかったので見送りましたが、自由席限定とはいえ、四国グリーン紀行(20570円)の半額未満というのは魅力的と言えます。巷でもよく言われますが、「若者限定」というあたりが、JR東日本とは対照的です。 駅前[④]。利用客が多い主要駅ということで、タクシーも多数待機しています。ホームを覆う壁は、窓ガラスの数や面積があまり多くなく、外からはホームの様子が窺いにくいです[⑤]。坂出・宇多津・丸亀と3駅連続で高架駅が続きますが、それぞれ「壁という壁はない」、「窓ガラスが多用され、中がよく見える」、「壁があり、窓も少なく、中は見にくい」とそれぞれ異なる造りをしています。 北口は「狭い路地が駅前まで来ている」といった具合で、閑静な住宅街が広がっています[⑦]。主要なホテルは南口に集中していますが、北口にも宿があり、駅を出てすぐそこの徒歩0分のところに「ザ・丸亀ゲストハウス」なる簡易宿泊所があります[⑧]。やたらと細く縦長で、見た目はちょっと怪しい(ゴメンナサイ)ですが、中は結構綺麗に整備されているようです。 丸亀駅構内にある、本州方面の新幹線接続表[⑩]。四国島内相互の移動需要というのは、やはりそこまで多いものではなく、「岡山での新幹線との接続を介した本州方面との行き来」が、JR四国にとっても生命線です。しおかぜ号や南風号、快速マリンライナー号による本州・四国連絡は、JR西日本にとっても重要であり、四国方面からの在来線列車が遅れると、接続する新幹線が待つこともあります。 特急用の定期券、「快て〜き」[⑪]。鳥取駅にも同様の商品の広告があり、そのときは「特急料金は全く割引になっていない」とご紹介しましたが、こちらの快て〜きは、特急料金も減免されていて、ちょっと計算してみると、1か月定期の場合、特急料金に相当する部分の金額は、だいたい20日分くらいとなっているようです。これなら本当にお得と言えます。 行動派の鉄道ファンならば知らない人はいない・・・と言っても過言ではないであろうトクトクきっぷ、「バースデイきっぷ」。”その人の誕生月に有効で、JR四国全線の特急列車のグリーン車指定席が3日間乗り放題”というもので、その価格は13000円[⑫]。以前は10280円でしたが、多少値上がりしたところで、そのお得度合いは揺るぎません。1度だけ使ってみたことがありますよね、コレ。 しおかぜ3号に乗車して、愛媛県の代表駅となる松山を目指します[⑬]。2本続けて特急が来るようです。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
  
|
|||||||||||||

|
|||||||||||||
しおかぜ3号・いしづち3号がやってきました[①]。宇多津で併結し、1つの編成となりました。私としては、ここは是非8600系に当たりたかった(8000系はもう何度も乗っていますからね)ところでしたが、充当されていたのは8000系でした。 「四国グリーン紀行」を使用しているということで、ここでは当然グリーン車に乗ります[②]。座席カバーは、普通車指定席で使われるものと同じで、青地に白字で「指定席」と書かれています。普通車とは異なり、1つの車両の中で自由席と混在しているわけではない(半室グリーン車ですが、もちろん仕切りがある)ので、無地のものにしてくれた方が、”グリーン車”の雰囲気は損なわないような気がします。 四国では、元々グリーン車の需要は高くありません。8000系・2000系・8600系にグリーン車がありますが、いずれも半室です。2月の平日だからということもあるかとは思いますが、このしおかぜ3号のグリーン車も、丸亀で私が乗り込んだ時点では、他には1人が乗っているだけでした[③]。フルムーンでの利用に対応するために申し訳程度に設定してある、といったところでしょうか。 予讃線では、随所に瀬戸内海の海原が展開されますが、それが最初に現れるのは、海岸寺〜宅間間です[④]。雲ひとつない快晴の下では、海の青色もより一層映えます。海沿いの区間を一直線に駆け抜けることから、ここは列車の撮影ポイントにもなっています。 9:28に宅間に到着[⑤]。2つ隣の高瀬共々、主に朝晩に、一部の特急列車が停車します。宅間に停車する下りの特急列車は、このしおかぜ3号で一旦終了となり、日中に運転されるしおかぜ・いしづち号は全て宅間を通過。次に停車する下り便は、19:37のしおかぜ・いしづち23号となります。 8000系は普通車・グリーン車ともに大窓ですが、グリーン車のそれの大きさは、これまた殊更に凄まじい[⑥]。普通車の座席間隔は980mmですが、グリーン車では1170mm。その1170mm間隔で配置される座席を2列分カバーするわけですから、その横幅は相当なものです。なお、8600系と2000系では、普通車は大窓・グリーン車は小窓という、国鉄時代の特急型車両に倣ったような仕様となっています。 ふと床を見てみると・・・、なんですか、これは[⑦]。座席と壁の間で、なかなか掃除が行き届きにくい個所であるということは承知しますが、それでも、ここまで豪快に埃やゴミが散らかっているグリーン車は初めてです。もちろん、普通車であっても、掃除はきちんとしてもらいたいものですが。ちなみに、ご覧のように、8000系では、グリーン車でも絨毯が敷かれていません。 私以外では唯一グリーン車に乗っていたそのひとりが観音寺で下車したため、観音寺から先は、このような貸切状態となりました[⑧] [⑨]。3席×6列=18席分の空間が私だけのものに。気兼ねなく過ごせるこの空間こそ、まさに”快適”と呼ぶにふさわしいです。 せっかくガラガラになったので、1番C席に移動してみました[⑩]。運転室と客室の間にもデッキがあるので、デッキを挟んでということにはなりますが、8000系のグリーン車では、一応前面展望が楽しめます。ただし、前面展望を意識したパノラマ仕様とはなっていない(デッキの件もそうですが、前面窓の下端の位置が高い)ので、そこはあしからず。 箕浦で上りのしおかぜ・いしづち号と行き違い[⑪]。アンパンマン列車といえば、2000系の専売特許のようなところがありましたが、現在は8000系にもアンパンマン列車仕様となっている編成があります。箕浦を通過すると到着する川之江では、121系の足回りをVVVFインバータ制御に換装した新形式車両、7200系と遭遇[⑫]。 四国中央市は、大手製紙会社・大王製紙の本拠地です[⑬]。車窓にもその工場や施設がたびたび現れます。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
  
|
|||||||||||||

|
|||||||||||||
JR四国の特急列車のグリーン車には、車内誌が備えられています[①]。「四国旅マガジンGajA」という雑誌で、ペラペラのパンフレットではなく、しっかりと製本された”雑誌”なのですが・・・、裏面を見てみると、「定価:本体920円+税」という表記が[②]。本来なら売り物として書店に並んでいるようなものを、車内誌としてグリーン車に置いているわけですが・・・、これ、持ち帰っても良かったのでしょうか? (過去の経験例から言うと、「この雑誌は車内でのみお読みください。お持ち帰りはご遠慮ください」というものは見たことがありませんが) ところで、車内誌といえば、東海道・山陽新幹線のグリーン車では、経済紙「Wedge」と旅行情報誌「ひととき」が備えられていますよね。これらは一般販売もされていて、その価格は共に「税込み500円」なのですが、いずれも、グリーン車で配布される仕様のものは、「ご自由にお持ち帰りください」と書かれています。都合1000円相当のプレゼントがあることと同義ですね。 振り子機構を活かしながら、線形に恵まれない予讃線を進みます[③]。いくら空気ばねによる車体傾斜機構が進化しても、所詮は「車体傾斜」にすぎず、その角度は振り子に敵うこともなければ、所要時間の面でも振り子を超えはしません。最近は、費用対効果の都合か、振り子式の後継が車体傾斜式になることが多いですが、「もし最新の技術で振り子式車両を造ったら?」と思わずにはいられません。 まもなく伊予西条に到着します[④]。伊予西条には、「鉄道歴史パーク in SAIJO」なる、実物の鉄道車両や鉄道に関する資料を揃えた展示施設があり(写真に写る「四国鉄道文化館」は、それを構成する施設のうちのひとつ)、時間があれば是非訪れてみたいところです。・・・と、ここで件の8600系が交換相手として登場[⑤]。 車窓に見える山脈の頂上は、いくらかの雪を抱いています[⑥]。四国といっても、山の上であれば、雪が降っても全くおかしくありませんが、そういえば、この旅が始まった(2月7日)あたりに、愛媛県の南予地方で、随分な大雪が降ったとか。確率的には相当低いですが、例え人が住む平地であっても、降るときは思いっきり降るわけですね。 伊予小松を通過すると、線路は大きく右へ曲がります[⑦]。その曲がりのきつさは相当なもので、列車内にいながら、これから進んでいく先の線路が、これほどにもはっきりと見えています。しかし、このような場所でこそ、振り子式車両の真価は発揮されるものです。 今治市街地に入りました[⑧]。愛媛県第2位の都市というだけあって、街並みはさすがに都会的。高架化された今治駅から見る市街地も(ちょっとしか見えませんが)、高い位置(高架線)からでも十分に認識できる背の高いものが多いです[⑨]。 菊間〜大浦、光洋台〜堀江で、列車はまた海に近いところを走ります[⑩]。砂浜も透けて見えるその透明度は、まさに”美しい”のひとこと。沖合の方の濃い青色も鮮やかで、一見しただけでは冬の写真とは判別しにくいような爽やかさに満ちています。 丸亀から約2時間で終点の松山に到着しました[⑪]。キハ181系時代(110km/h運転を行っていた末期)は、丸亀〜松山間は2時間25分弱ほどで結ばれていたようなので、やはり車両性能の差(電車、最高時速、振り子)は大きいようです。 |
|||||||||||||
TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |




































