 Page:115 ※各画像はクリックすると拡大します。 |
||||||||||||||
  
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
駅前は、氷が薄く張っていて、スケートのように滑ることが可能な状態でした[①]。スーツケースを放置すると、その傾斜と滑りやすさのせいで、ずるずると勝手に走っていく始末。片方の手は、常にスーツケースに添えておきます。 跨線橋の全体図[②]。木材の深みを増した茶色が、雪の白さと対照的です。屋根に積もっている雪の量は少なく、除雪作業員によって定期的に雪下ろしがされていることが分かります。屋根に上るために取り付けられていると思われる梯子も、複数個所で確認できます。木造部分の割合も高いので、雪が大量に積もったまま放っておいたら、本当に崩落しそうですからね。 駅前を通過する国道5号線[④]。当然ですが、車道用の信号機は、雪国に特有の縦長仕様のものです。LED化はまだされておらず、旧来からの白熱灯が光源として使用されていましたが、雪国では、この方が都合が良いとも言われています(電球の発熱によって、信号機の表面に付着した雪が融け落ちるため)。 国道5号線の様子[⑥] [⑦]。車道の除雪は、ほぼ完璧と言って良いくらいに完遂されていて、アスファルトは全面的に露出しています。ここに限って言えば、ノーマルタイヤでも通行に支障はなさそうです。その代わり、除雪した雪は、あくまでも「横に移される」だけなので、溜まりに溜まった雪は、その高さを伸ばし続けています[⑧]。 「車道の除雪は」という言い方をしたからには、歩道について触れなければなりません。歩道の除雪状況はというと・・・、こちらは、車道ほどに徹底してはいません[⑨]。両側に積み上がった雪は、場所によっては、人の背丈ほどに達しています。路面は、足跡が残るくらいには雪が積もっていて、私も小沢駅前の歩道に”足跡”を残してきました。 積もった雪によって、バス停の標示が見えにくくなってしまっています[⑩]。もちろん、バスの運転士は、ここに小沢駅前のバス停があることは把握しているでしょうから、「バス停の存在に気が付かなかった」とはいかないはずですが、この雪の積もり方からすると、標示も利用客も、ちょうど雪だまりの影に隠れてしまいそうです。 駅舎内部[⑪]。無人駅ですが、状態はかなり良いと言えます。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
 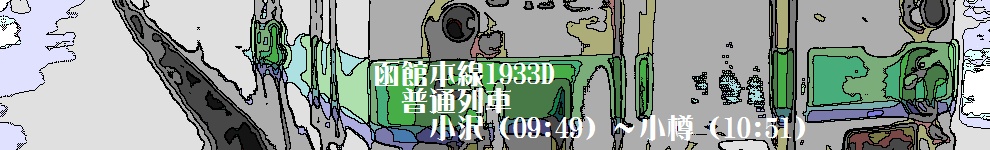 
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
小樽行きの列車に乗ります[①]。先ほど乗車した倶知安行きの折り返し列車です。キハ40形とキハ150形が連結しているとなれば、当然キハ150形の方を選びます。単純に、その方が「新しくて綺麗」ですからね・・・。 巻き上げた雪が水滴となって付着している車両後部[②]。本当に寒いときは、シャーベット状に凍り上がりますから、今日はちょっと寒さが足りないのかもしれません。わざわざこんなところにいることからも分かるように、車内は意外と混み合っていて、「良いポジション」の座席にありつけそうになかったので、2両目の車両最後部に立っていました。 然別で列車交換[③]。今朝乗車した2両編成のキハ150形と行き違いました。このときになってようやく気が付いたのですが、相手のキハ150形は、手前の1両目が0番代で、奥の2両目が100番代でした。外見においては、窓の構造に大きな違いがあり、前者が大型の固定窓で、後者が小型の開閉可能窓となっています。なお、前者は冷房付きなので、夏季はぜひ0番代に。 小樽の市街地が見えてきました[⑤]。長万部は、特急停車駅といっても小さな町でしたし、新函館北斗は、函館市ですらない(北斗市)中でもその外れでしたから、これくらいの街並みを見るのは、もしかしたら、青森駅以来かもしれません。”街”としての雰囲気を見せる車窓の中に架線が現れると、列車は終点の小樽に到着します[⑥]。 そして列車は終点の小樽に到着[⑦]。倶知安やニセコは、今、外国人観光客からとてつもない人気を誇っているので、”山線”と呼ばれる区間において外国人の姿が見られることは、全く珍しいことではありません。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
  
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
11:00ちょうど発の快速エアポート114号に乗り継ぎます[①]。その名前が示す通り、この列車は新千歳空港行きです[②]。その反対側の始発駅(終点駅)は、小樽・札幌が基本ですが、石狩当別・手稲を始終着駅とする便が、それぞれ1日1往復のみ設定されています(当時)。 札幌までの利用ですが、乗車するのは、もちろんコレ[④]。指定席uシートです。快速エアポート号は、その速達性の高さによる利便性から、空港に向かう人たち以外もよく乗っているため(自分もその一人ですが・・・!)、終日人気があります。その混雑から逃れ、快適に移動するのであれば、やはりuシートの利用は外せません。 リクライニングシートを備えた指定席車両ということで、車内は特急列車のような雰囲気です[⑤]。車内の一部は、座席を配置せずに荷物置き場としていて、大型のスーツケースを持ち込む需要への配慮を行っています。快速列車なので、特急料金は不要であり、uシートの利用に際して必要なものは、530円(2019年10月〜)の指定席券のみです。 小樽築港〜銭函間は、海沿いも海沿いというほどに海岸線ギリギリを走る区間となっていて、これは北海道内でも有数の名車窓のひとつです。当然、小樽〜札幌間では、海側の席を選びたいもの。快速エアポート号のuシートで海側になるのは、「A席」です[⑥]。ただし、窓割は、普通車自由席の車両と同じなので、窓割と座席配置が合っておらず、A席であっても「外れ」が存在します。 小樽築港でDE15形のラッセル車に遭遇[⑦]。両端にラッセルヘッドを連結した状態で待機していました[⑧]。車両番号の銘版は、ラッセルヘッドにも付いていて、それは機関車本体と同一でした(DE15-1542)。つまり、ラッセルヘッドそのものは、独立した形式を持つ車両としては認定されておらず、あくまでもその機関車の付属物という扱いのようです[⑨]。 海沿いの区間に入りました[⑩]。線路は、まさに海岸線の形に沿うように敷設されていて、右に左に何度もくねります。小樽からの函館本線は、複線電化となっているため、札幌方面に向かう下り列車においてこそ、真の「海景色」を眺めることができます[⑪]。上り列車では、「下りの線路越し」になり、海から離れてしまいますからね。 海越しに小樽市街を眺めます[⑫]。天気が悪く、視界もイマイチ。函館本線のこの海沿いの区間は、何度か乗車したことがありますが、たいてい天気が悪く、なかなか「青空の下に広がる大海原!」という車窓にありつくことができていません。まあ、冬の荒れた海は、それはそれで「北国の厳しい冬」といった雰囲気が醸し出されないこともないので、一応価値はあります。 突然に現れる恵比須島[⑬]。”島”とは言ったものの、見ての通り、実質的には”岩”です。小樽築港〜銭函間の海沿いの区間は、その視界を遮るものが現れることがほとんどなく、沖合に小島などもないため、この恵比須島は、非常に目立ちます。 内陸部に入り、ほしみ駅を通過しました[⑭]。「札」の表示があるように、ここはもう札幌市内です(同駅は、同市で最も西に位置する駅)。この旅の終わりとなる札幌駅も、かなり近いところになっています。 |
||||||||||||||
TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |































