 Page:77 ※各画像はクリックすると拡大します。 |
||||||||||||||
  
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
甲府駅は、JR東日本が管轄している駅ですが、4番線・5番線は、身延線専用のホームとなっています。そのため、同ホームの駅名標は、JR東日本仕様のものでありながら、JR東海の橙色を纏っているという、一風変わった様式のものとなっていて、目を惹きます[①]。 JR東海の313系[②]。甲府駅では、身延線の列車としてしか姿を現しませんが、中央東線と辰野で接続する飯田線、塩尻で接続する中央西線から(へ)中央東線に乗り入れる普通列車が数多く設定されているため、「中央東線を走る313系」そのものは、珍しいものではありません。 4・5番線の線路は行き止まりとなっていて、ここで線路が途切れます[③]。よって、ここに入ってくる身延線の列車というのは、必ず甲府始終着となります。甲府駅の配線を見ると、身延線と中央東線(塩尻方面)の相互直通は可能なようですが、そういった列車の設定はありません(最近、小淵沢発着の「諏訪しなの」なる列車が設定されているので、「諏訪ふじかわ」を走らせてみるのはどうでしょうか?)。 313系と373系が並ぶ身延線ホーム[④]。この眺めだけを見ると、いかにもJR東海の駅という雰囲気ですが、JR東日本様式の番線表示とacureの自動販売機が、ここがJR東日本の駅であることを教えてくれます。 2018年3月のダイヤ改正で引退することとなっているE351系がやってきました[⑥]。JR東日本における最初で最後の振り子式車両という特徴を持っていたこの形式も、特に保存が行われることはなく、全車両が解体されました。波動輸送に転用されることもなかったので、結果として、定期のあずさ号・かいじ号から引退し、細々と臨時列車に使われ続けていた183系・189系よりも先に形式消滅しました。 グリーン車の中央部に見える、窓がない部分[⑦]。外見上の特徴のひとつとなっていますが、これは、1両のサロE351を、中央で喫煙区画と禁煙区画に分けていたころの名残です。この窓がない部分には仕切りがあり、それによって喫煙/禁煙に二分していましたが、当然、喫煙区画から禁煙区画への煙の流入が多発したため、1両丸ごと禁煙になりました。 甲府駅を発車するスーパーあずさ14号[⑧] [⑨]。車体を大きく傾ける振り子式車両らしく、車体は卵型に絞り込まれていますが、一方で、屋根上には空調機器が設置されていて、徹底的な低重心化を目指した381系(空調機器を全て床下につけたため、屋根には何もない)のような「スッキリ感」はありません。もっとも、これは383系でも同様です。 甲府駅構内に留置されていたEF64形37号機[⑩]。茶色一色の塗装が特徴的です。2009年3月のダイヤ改正で、寝台特急あけぼの号の上野〜長岡間の牽引機がEF64形となった際、38号機(国鉄色)と共にその充当機に指定されたため、当時は大きな話題を呼びました。現在は工臨の牽引に当たったり、カシオペア紀行の牽引に当たったりしているようです。 E353系は、2017年12月から営業運転への投入が始まりましたが、主たる置き換え対象たるE351系が、12両(8両+4両)×5本=60両という小所帯であったため、その総置き換えには、さほど時間はかからず、翌年3月のダイヤ改正で、E351系は全てE353系に置き換えられました。E353系を「新型特急」と呼んでE351系と区別する必要があったのは、僅かな期間でした[⑫] [⑬]。 中央東線のホームで使用されている駅名標は、よく見慣れたJR東日本様式のものです[⑭]。しっくりきますね。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
 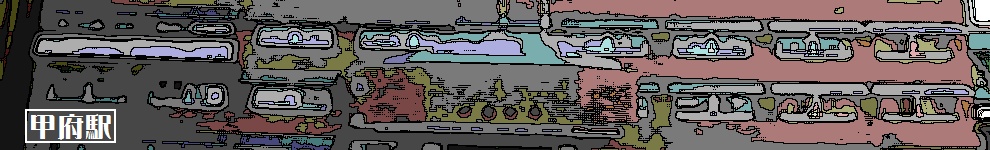 
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
山梨県の代表駅となるのが甲府駅です[①] [②]。主要な駅ですが、橋上駅舎だけを持っているということもあってか、改札口はひとつしかありません。もっとも、同じ”県庁所在地クラス”という意味では、これは水戸駅や前橋駅でも同様です。 甲府駅のびゅうプラザは、2018年3月をもって閉店しました[③]。以前から、JR東日本では、みどりの窓口とびゅうプラザを、とてつもない勢いで閉鎖させ続けていましたが、このときは、「県庁所在地の駅でびゅうプラザが消えるとはどういうことか?」と思いました。そしてその後、2019年6月、JR東日本は、それこそ東京や新宿等も含めた、管内の全てのびゅうプラザを閉鎖する意向を示しました。 甲府駅前の様子[④] [⑤]。ホテルや商業施設が立ち並ぶ、まあ、ごくごく平凡な「地方都市の駅」といったところ。甲府市は山梨県の県庁所在地ですが、その人口は約18万8000人(2019年6月)であり、これは全国の県庁所在地の街としては、最も少ない数値です。ただし、甲府市は、人口拡大を目指した”いたずらな合併”はあまりしていません(それゆえ、面積は212km2程度)。 ”甲府盆地”と呼ばれるように、甲府市は、周囲を山々に囲まれています。雪を頂いた山々の立ち姿は美しく、山梨県は、海がない代わりに、秀麗な連峰の眺めが、訪れる人の目を楽しませてくれます[⑦]。 駅ビルと一体化した駅舎[⑧]。このような佇まいの駅舎を見ると、徳島駅のハリボテ駅舎を思い出してしまうのですが・・・、大丈夫です、甲府駅は、裏手側にもちゃんと街がありますので・・・。 甲府駅では、乗り継ぎの都合上、1時間30分ほどの待ち時間があります。「これくらい長めの待ち時間があるならば・・・」ということで、山梨県庁にやってきました[⑨] [⑩] [⑪]。以前にも触れたことがありますが、当初の構想では、47都道府県すべての代表駅を訪れるだけでなく、その全ての都道府県庁舎も訪ねる予定でした(が、それをやると更に日数がかかるので、結局断念)。 お昼時ということで、単に県庁を訪れるだけではなく、その地下食堂で昼食を食べました[⑫]。「甲府では待ち時間がある」、「県庁には一般にも開放している食堂がある」ということは、事前の調べで把握していたので、「それならば、県庁に行った記念に」ということで、ここを昼食の場に選びました。今回の旅の2日目で、沖縄県庁で昼食を摂りましたが、県庁で食事をするのは、それ以来のことです。 13:29発の特急スーパーあずさ15号に乗車します[⑬]。感づいていた方もいらっしゃったかとは思いますが、甲府で1時間30分ほどの待ち時間があるといっても、それは、別に特急あずさ号の本数が少なく、そうするほかなかったから、というわけではありません。旅程を練っていたとき、「13:29まで待てば、E351系のスーパーあずさ号がある」ことに気がついたため、このようになりました。 E351系によるスーパーあずさ号の乗車位置案内のところで列車を待ちます[⑭]。この絵、よく見てみると、正面の愛称表示機のところが「あずさ」となっています。1993年の登場直後は、スーパーではない、普通の臨時「あずさ号」で使われていたため、ある意味懐かしい姿を再現していると言えます(その後も、代走で普通のあずさ号で使われることがたまにあった)。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
  
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
スーパーあずさ15号が入線します[①]。高運転台にLEDの愛称表示機という面構えは、かつて地元常磐線を走っていた651系を彷彿とさせるものがあり、そういう意味でも、私はE351系が好きでした。 今回は普通車指定席に乗車しました[②]。甲府〜塩尻間の営業キロは88kmで、グリーン車に気軽に乗れるチャンス(100km未満なので)でもありましたが、前回のE351系への乗車のときがグリーン車だったこと、そして今日が閑散期(普通車指定席とグリーン車の差額は710円となる)ということもあり、普通車指定席に落ち着きました。 竜王を通過します[③]。1日に2往復、甲府から1駅だけ足を延ばし、竜王を始終着とする特急かいじ号の設定がありますが、あずさ号は全て通過します。なお、竜王が始発・終着となる列車は、そのかいじ号だけで、普通列車には、そのような列車はありません。 山々を横目に見ながら、中央東線を駆け抜けていきます[④]。振り子式車両という特殊仕様もあり、E351系は、ずっと中央東線・篠ノ井線・大糸線で使われました(他の路線に転用しようにも、地上設備が対応していない)。振り子を固定すれば、波動輸送用の車両にするという道も開けた可能性はあるかと思いますが、その装置の存在そのものが維持費の高騰を招くことはたしかでしょう。 高尾行きの普通列車と遭遇[⑤]。中央東線の普通列車=115系という時代も終わり、現在は、立川以西を走る中距離電車は、あらかた211系になりました。115系と比べれば、211系は新しくて綺麗と言えるのかもしれませんが、”E”を冠する新世代の車両に慣れると、正直、211系は、古いし揺れるしうるさいし・・・と思います(私の感想としては)。 茅野に停車[⑥]。これまで、中央東線の特急列車は、八王子・甲府・茅野・上諏訪は、全ての列車が停車していました。しかし、2019年3月のダイヤ改正より、上諏訪については、1日に1往復、これを通過とする便が現れました。JR東日本いわく、「利用実態の考慮と所要時間短縮のため」とのことですが、所要時間を引き合いに出すなら、E353系に対し、なぜ振り子ではなく車体傾斜を採用したのでしょう・・・。 上諏訪駅の留置線で並ぶ、JR東日本の211系とJR東海の213系[⑦]。一応、211系と213系の混結は可能ですが、そのような「異会社の異形式が混結する」という興味深い事象は、残念ながら実際には起こっていないようです。 上諏訪駅付近では、左手に諏訪湖が見られます(少しだけ・・・)[⑧]。毎年8月・9月には、ここで大規模な花火大会が開催され、その帰宅用に、上諏訪発新宿行きの臨時夜行快速列車も運転されます。E351系は、その臨時快速に充当された実績もあり、スーパーあずさ号として振り子を生かしながら走る「表の顔」とは裏腹な、振り子も使わずに寝かされたスジでゆっくりと走る「裏の顔」を見せていました。 振り子を作動させ、車体を大きく傾けるE351系[⑩]。E351系の醍醐味を実感できる瞬間です。私は、E353系に乗ったこともありますが、空気ばねによる傾斜角度1.5度では、曲線に差し掛かっても、それによって傾いているということには気づきにくいです。一方、E351系は、振り子によって5度も傾くので、否が応でも分かります。もっとも、車内販売員にとっては、”過酷”らしいですが。 岡谷を過ぎ、みどり湖経由の短絡線に入ります。山を貫くトンネルを駆け抜けることにより、岡谷〜塩尻間の距離は、辰野経由の27.7kmに対し、みどり湖経由は11.7kmとなっています[⑪]。塩尻駅の手前で、辰野経由の旧線と合流します[⑫]。 そして列車は下車駅の塩尻に到着しました[⑬]。スーパーあずさ15号は、当然、松本まで走るのですが[⑭]、松本まで行くと、甲府からの営業キロが101.3kmとなり、ぎりぎりで100kmを超えてしまいます。よって、特急料金節約のために、塩尻で降りることとしています。 |
||||||||||||||
TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |









































