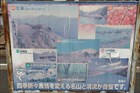Page:50 ※各画像はクリックすると拡大します。 |
|||||||||||||
 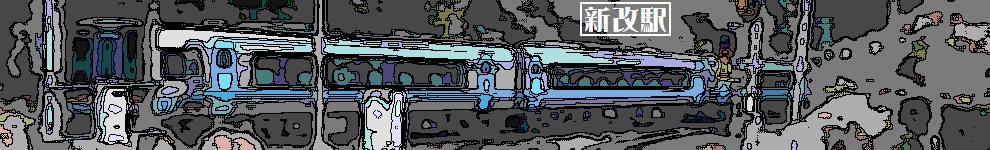 
|
|||||||||||||

|
|||||||||||||
典型的な秘境駅と言える新改駅ですから、他に降りる人などいるわけがありません[①]。ましてや、今は青春18きっぷが使える時期でもありませんからね。2月の月〜木は、特急の繁閑カレンダーで閑散期に指定されることからも分かるように、2月の平日というのは、鉄道で旅に出る人が多い頃合いではないわけです。 5両編成分くらいの長さはありそうなホームですが、この写真からも分かるように、乗降がしやすいように嵩上げされているのは、1両分のみであり、もはや2両以上の列車が入線することは想定していないことが分かります[③]。もっとも、嵩上げされた部分でさえも、1000形の床との段差は、かなりのものがあるようですけれども・・・。 スイッチバック構造をとる新改駅ですから、すぐに発車するというわけにはいきませんね[④]。これから琴平方面へ進んでいくために、本線上を横断し、引き込み線に入りますが、その前に、まずは下りの特急南風号を先行させます[⑤]。通過列車は、新改駅のホームは通りませんから、乗客は、この駅の存在に気付かないかもしれません。ホーム自体も、こんな林に隠れていますからね[⑥]。 上り列車に対する信号機が(考えたら、上りと下りの信号機が同じ側・同じところにあるのは、スイッチバック駅ならではですね)注意現示に変わったので、出発できるようになりました[⑦]。扉を閉めた列車が、引き込み線に向かって動き出していきます[⑧]。琴平側の前頭部は、入換灯状態となっていました[⑨]。そして引き込み線から再度本線に戻り、列車は琴平方面へ走り去っていきました[⑩]。 列車がいなくなってしまった新改駅は、まさに閑静そのもの[⑪]。気動車のエンジン音が唯一と言っても良い”音”だったのに、それがなくなってしまったわけですから、そりゃあ静かだというものです。林に生い茂る木々の隙間から、1軒の民家が覗いていましたが、とても人が住んでいるような様子ではありません[⑫]。というか、そもそもどうやってあそこへ行くのか? 辺りはとにかく山、山、山[⑬]。明るい昼間だからまだ良いですが、夜なら不気味なことこの上ないはずです。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
 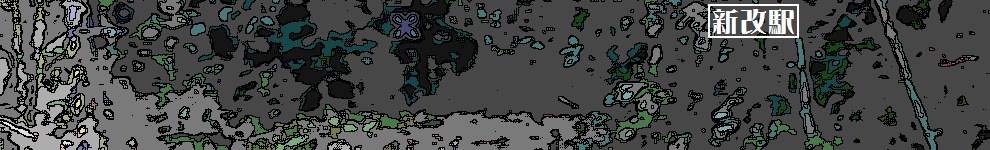 
|
|||||||||||||

|
|||||||||||||
ホームに引き込まれた線路は、草むらの中で途切れます[①]。スイッチバック駅である以上、この先に線路が伸びることはありません。車止め・・・というほどのものはなく、そこには、線路の終端を示す標識が置かれているだけであり、2条のレールは、まるで自然の中に溶け込むように消えてしまっています。 5両編成の停止位置目標を示す標識[②]。これがあることから、少なくとも、5両分のホーム有効長は確保されていることが分かります。なるほどたしかに、ホームの端からもう一方を眺めてみると、その長さが極端に短いということはありません[③]。しかし、先ほども述べたように、通常使われるのは、嵩上げがなされた1両分のところのみであり、残りの部分は苔だらけです。 山奥にある小さな駅ですが、雨をきちんとしのげるだけの駅舎が設けられています[④]。とても入る気にはなれませんでしたが、便所もあるほか、運輸関係者が詰める部屋も作られているようです。駅舎内も、例えばゴミだらけであるとか、虫だらけであるとか(まあ、今は冬ですが)、埃だらけであるとかいうことはなく、きちんと掃除が行き届いています[⑤]。 同じ四国の秘境駅でも、例えば坪尻駅は、道路からは隔離された地帯にあり、熊も出る山道を通り抜けた先に駅がありますが、新改駅は、駅舎のすぐ前まで舗装路が来ています[⑥]。もちろん、決して広くはなく、また、ここに至るまでの勾配とその曲がりくねり方はかなりのものがありますが、自動車の乗り入れは可能です(ですから、今回はタクシーを呼んであります)[⑦]。 駅舎外観[⑧] [⑨]。中の待合室も綺麗でしたが、駅舎そのものもまずまず綺麗です。うっすら苔が生えてはいますが、塗装が劣化しているとか、部材が朽ちているとか、そのようなことはありません。そして興味深いことに、この駅舎は、1947年の駅開業時からのものが使われ続けているそうで、これでも築70年以上なのです。 保線要員等が詰めると思われる部屋[⑩]。ここは滅多に人の出入りがないからなのか、あるいは客の目につかないところだからなのか、いささか汚れていました。山奥ということで、冬は冷えるのか、ストーブもバッチリ完備しています。よく見慣れたデザインのペットボトル飲料が、ここに人の出入りがあることを示しています。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
  
|
|||||||||||||

|
|||||||||||||
ところ変わって、ここは土佐山田駅前[①]。新改駅前に予め呼んでおいた(昨日、宇和島駅で電話予約をしておきました)タクシーに乗り込んで、土佐山田まで移動してきました。一応、1時間10分ほどの滞在時間で、高知方面の下り列車を捕まえることはできたのですが、そうすると、この先の旅程に支障をきたすため、先を急ぐべく、タクシーを使いました。 今回お世話になったのは、駅前のすぐそこにある浜田ハイヤーという会社でした[②]。「新改駅に来てほしい」という依頼はそれほど珍しくもないということなのか、予約のために電話をかけたら、二つ返事で了解が貰えました(「それ、どこ?」とかは言われませんでした)。 JR四国は「アンパンマン列車」を運行していますが、ジェイアール四国バスは「アンパンマンバス」を運行しているようです。土佐山田駅前からは、同社の大栃線が出ていますが、その乗り場は「アンパンマンバスのりば」と銘打たれ、わざわざこのような装飾まで施しています[③]。 駅舎[④]。・・・というより、コンビニ? 土佐山田駅に入居している売店はセブンイレブン(キヨスクから転換)ですが、「土佐山田駅」と書いてある部分よりも、セブンイレブンのロゴといつもの3色帯が掲げられている部分の方が、面積が大きいです。まるで駅の方がおまけであるかのようです。「三角屋根のコンビニなんて、これまた随分とお洒落なことで〜」。 セブンイレブンは、言うまでもなく、全国的に展開しているコンビニです。しかし、店舗の外にある、店内設置のATMで取り扱えるキャッシュカード(銀行)の一覧を見ると、そこには、四国銀行・高知銀行・伊予銀行・・・とあり、ここから「四国のセブンイレブンであること」が読み取れます[⑥]。全国チェーンのコンビニは、良くも悪くも全国均質ですが、こんなところに”地域性”は反映されるわけです。 2面3線の土佐山田駅[⑦]。典型的な「国鉄線における中規模駅」の配線構造です。中線に停まっている車両は、「窪川」を行き先として表示していますが、次に土佐山田を出る窪川行きは、16:12発の始発の窪川行きまでないので、このまましばらく小休止するようです。 洗面台の残骸[⑨]。顔を洗うための洗面台だったのか、それとも水飲み用の蛇口だったのか、この残骸からは読み取れません(まあ、造りから言って、後者なのかなとは思いますが)。そのくすんだ色合いが、使用停止から今日に至るまでの時間の長さを暗示します。 香美市の観光スポット案内[⑩]。この街が自然豊かであることはよく分かりますが、あまりに色褪せているのと、長期間にわたって放置されたことでできてしまったひび割れや剥離のせいで、写真に見える風景の美しさが損なわれてしまっています・・・。 駅構内に、1個の国鉄コンテナが置かれていました[⑫]。鉄道貨物用としては用をなさなくなったコンテナが、倉庫代わりとして個人や民間企業に払い下げられることはよくありますが、柵の内側にある=土佐山田駅構内にあるということは、JR四国がこれを倉庫として使っているということでしょうか。が、ここまで朽ちていると、もはや使われていない可能性もあるかもしれませんが。 下りの特急南風11号がやってきました[⑬]。ここで私が乗車する上りの南風20号と列車交換を行うため、すぐには発車せず、しばらく停車します。 |
|||||||||||||
TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |