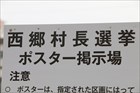Page:92 ※各画像はクリックすると拡大します。 |
||||||||||||||
  
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
新白河というだけあって、この駅は白河市にある。それが、大方の見方でしょう。しかし、実際には異なります。西口の駅前に出て目に飛び込んでくるのは・・・、”西郷村長選挙”のポスター掲示場[①] [②]。新白河駅は、新幹線の停車駅で、かつ”白河”を含みながらも、実際には、西郷”村”に所在しています(駅の一部は白河市にかかるが、駅の所在地は駅長室の場所で決まる)。 ただいまの気温は3度、とのこと[④]。この日の白河市の最高気温は3.2度だったらしいので、今がちょうど1日で一番暖かい時間帯でした。2018年2月の白河市は、5〜8度くらいまで上がる日が多かったようなので、今日は寒い日でした。ちなみに、今日の最低気温は-2度でしたが、-3〜-8度くらいまで下がることが多かったのと比較すると、逆にこれは暖かいものでした。 人も少なく、少々閑散としている新白河駅構内[⑤]。ちょうどお昼時で、かつ次の列車までの待ち時間もそこそこあったので、ここで駅弁を購入し、昼食を摂ることとしました[⑥]。「福豆屋の牛めし」なるこの駅弁は、福島県産の牛肉を使用したお弁当で、本来は郡山駅で販売されているもの(掛け紙にもそう書いてある)ですが、新白河でも売られています。 12:03発の黒磯行きに乗車します[⑦]。あの車止めの向こう側、件の6番線から発車する列車です。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
 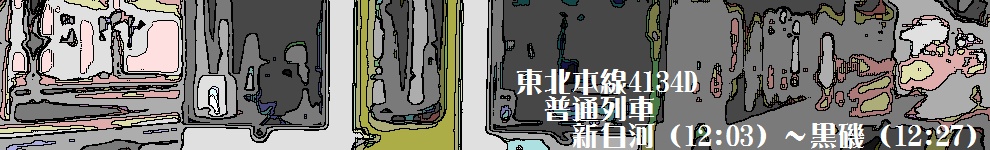 
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
こちらが12:03発の黒磯行きです[①]。使用車両は、キハ110系2両編成。交流と直流が高久〜黒磯間で切り替わりますが、交直流区間を跨ぐ方法は、交直両用電車を充てること以外にもあります。そう、気動車ですね。現在、新白河〜黒磯間を走る列車には、電車のE531系以外にも、気動車のキハ110系も使われています。 東北本線は、全線が電化されていますから、当然、この列車も、終点の黒磯まで、ずっと架線下を走ります[②]。まあ、いくら交流と直流を直通する車両が必要になるといっても、正直にE531系を量産するのでは、割に合わないのでしょう。ただ、そこで「だったら気動車だ」というのは、羽越本線の村上〜間島間を越えて走る普通列車が、全て気動車なのと同じで、どこか貧乏くさい感じが・・・。 白坂〜豊原間にある黒川橋梁を渡ります[③]。東北本線を上ってくる寝台特急列車の撮影地として非常に有名な場所であり、全長約350mのまっすぐな橋梁は、長編成の列車が非常に映えるものでした。が、翻って、いま私が乗車しているこの列車は、たった2両編成。ああ、短い、なんと短いことか。これでは撮影のし甲斐がありません。 終点黒磯のひとつ手前、高久に到着[④]。福島県にある東北本線の駅としては、最も南に位置する駅であり、次の黒磯からは、栃木県となります。県境越えを挟む新白河〜黒磯間は、やはり旅客需要もあまりないのか、本数は少なく、黒磯に至るまでに、下りの旅客列車とすれ違うことはありませんでした[⑤]。今の時間帯は、1編成のピストン輸送で事足ります。 東北新幹線の線路が横にやってくると、まもなく終点の黒磯です[⑥]。最終的には、地上在来線・高架新幹線というように分かれますが、黒磯駅の手前では、ほんの少しだけ、両線の目線の高さが同じになります。そして列車は黒磯に着きました[⑦]。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
 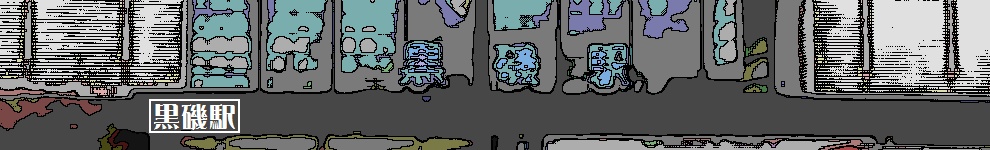 
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
新白河から2両編成の気動車列車に乗ってきましたが、元来、東北本線というのは、それはもう一大幹線でした。そんなわけで、この列車が到着した4・5番線ホームの有効長は、約300mほどがあり、これは即ち、20m級の在来線車両15両が停車できるということになります。階段に近いところに停まるために、列車はホームの端に停車するので、とてつもない長さが余っています[①] [②]。 黒磯駅駅名標[③]。黒磯からは栃木県になり、グリーン車を連結したE231系も数本やってくるうえに、路線愛称”宇都宮線”の使用が開始されるので、一気に「関東にやってきた」という感が強くなります。逆に、ひとつ手前の高久までは、福島県ということもあるので、そこはやはり”東北”という感覚が大きいです。 在来線の黒磯駅のすぐ横を、東北新幹線の線路が通過しています[④]。もう本当に真横も真横なので、黒磯駅に新幹線の駅があってもおかしくないくらいです。実際、それは真実で、東北新幹線の建設にあたっては、西那須野駅と黒磯駅のどちらに新幹線駅を置くのかで揉め、最終的に、その間にあった東那須野=現在の那須塩原に落ち着いたという出来事があります。 4・5番線から発車する下り列車と、接続する上り列車の両方を表示する発車標[⑤]。いま乗ってきた列車は、黒磯12:27着で、それに対して最も早く発車する上り列車は、黒磯12:51発です。鉄道好きとしては、黒磯駅で少しのんびりする時間が得られるので、これくらいの待ち時間があるのはありがたいことなのですが、一般旅客からすると、「待ち時間、長すぎ」と言われそうです。 駅の東西を結ぶ自由通路は、水平ではなく、途中でへの字型に曲がる、妙な構造になっています[⑥]。西側(写真右側)は、東北新幹線の高架下をくぐっているので、そのままの高さで水平に延長すると、架線柱等の設備に接触してしまうということなのでしょう。階段ではなく、への字型のスロープで高さを稼ぐことは、ある意味では、バリアフリーに対する先見性があったといえます。 黒磯駅周辺の見どころを案内する看板[⑧]。いかにもレトロな感が漂っていて、少なくとも、平成になってからの代物でないことは、誰の目にも明らかです。左上に「ビバ・ホリデー」とあるのが気になりますが、これは、1976年10月から、国鉄が私鉄と共同で始めたキャンペーン・・・らしいのですが、詳しい情報は、色々と検索してみても見当たりませんでした。 このとき、黒磯駅では、西口広場の整備工事が行われていて、駅前はまさに工事中でした[⑨] [⑩]。今回の旅では、自動車を運転することがないので、特に問題はありませんが、ドライブの旅をするときは、事前に衛星写真やストリートビューで得ていた情報と、実際の状況が異なる(このように工事が行われているなど)ことがあり、ちょっと困ります。 黒磯駅舎[⑫]。見た目は、ほぼ「新幹線の構造物と一体化した駅舎」であり、新幹線の駅があったとしても、驚きはないといえます。いや、むしろ、このような外観をしているというのに、新幹線は華麗に駆け抜けていくということの方に、いくらかの驚きがあるかもしれませんね[⑬]。西那須野共々、新幹線の線路はすぐそこにあるものの、乗り場がありません。 かつて東北本線の列車で使われていたサボが、黒磯駅の駅舎内で展示されています[⑭]。ここで目に留まるのは、「浦和通過」と書かれた池袋発着のサボでしょうか。1988年3月から、東北本線・高崎線の池袋乗り入れが開始されたので、そのときに使われていたものと思います。いわば現在の湘南新宿ラインの前身であると言うことができます。 |
||||||||||||||
TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |