 Page:108 ※各画像はクリックすると拡大します。 |
||||||||||||||
  
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
特急つがる3号に乗ります[①]。E653系とよく似ている(当然、これがベース車両)外観をしていて、真正面に列車名等を表示するための場所が設けられている点も共通しています。ただし、E751系は交流専用車両であり、直流区間への乗り入れはできません。そのため、2000年に「スーパーはつかり号」として走り始めて以来、ずっと北東北を走っています(函館には行かなかった)。 男鹿線と接続する追分を通過します[②]。追分は、臨時のリゾートしらかみ号も含め、快速以下の列車は、基本的に全て停車しますが、優等列車は通過します。かつての特急たざわ号は、その一部が停車していたこともありました。個人的には、今のつがる号を停車させても良いような気がします。正直、特急とはいっても、全然俊足ではない列車なので・・・。 線路沿いに設置された、大量の太陽光パネル[③]。春〜秋はともかく、日照時間がかなり減少する冬場は、どのくらい役に立つのでしょうか?日照時間もそうですし、パネル表面への積雪という問題もあるでしょう(当然、対策はしているはずですが)。 男鹿線からやってきたキハ40系と遭遇[④]。2017年3月より、新型の蓄電池駆動車EV-E801系の運用が開始されていますが、まだ1編成しか導入されていないので、男鹿線においては、まだキハ40系の方が主役です。とはいえ、烏山線が全て蓄電池車両に置き換えられたように、男鹿線のキハ40系が置き換えられるのは、決して遠い話ではないと思います。 八郎潟の干拓地帯に入りました[⑤]。干拓によって陸地となった場所なので、起伏もなく、とにかく平らです。晴れていれば、ここから男鹿の山々を眺めることができ、リゾートしらかみ号等の臨時観光列車では「進行方向左手をご覧ください・・・」といった案内放送も流れる、奥羽本線における名車窓のひとつなのですが、今日は雲に覆われて見えません[⑥]。 時間帯的には、ちょうどお昼時です。また、今は、つがる号という特急列車に乗車しています。そこで、つがる号の車内で食べることを前提に、秋田駅で昼食を仕入れました[⑦]。大館駅の駅弁として名高い鶏めしは、秋田駅でも販売されています。今回は、通常の鶏めしよりも少し豪華な、「比内地鶏の鶏めし」を選択[⑧]。掛け紙も和紙風になっていて、外面にも高級感があります。 中身はこのような感じ[⑨]。知っている人は知っていますが、比内地鶏の鶏めしは、”通常版より豪華(900円→1180円)”であるにも関わらず、肝心の鶏めしの部分は減っています。その代わり、おかずが少し充実・・・してはいますが。「通常版はもう食べ飽きた」とかでもない限りは、私は、通常版の赤い掛け紙の鶏めしをオススメしたいと思います。 東能代に到着[⑩]。ここで五能線と接続しています。「東能代」という名前の通り、この駅は、能代市街地からは外れたところにあり、街の中心部へ辿り着くためには、五能線に乗り換えて、ひとつ隣の能代を目指す必要があります。一方で、東能代は、幹線の奥羽本線にあり、鉄道の利便性は、こちらの方が高いです。これは、新前橋と前橋の関係に似ていますね。 東能代駅構内の分岐器[⑪]。融雪機でも仕込まれているのか、ここだけは、雪が全くありませんでした。これならば、分岐器の不転換も起こりませんね。分岐器は、雪害が発生しやすい設備のひとつなので、これの管理は大切です。 鷹ノ巣は、秋田内陸縦貫鉄道と接続する駅です[⑬]。田沢湖線も奥羽本線も、もう何度か乗車の経験があるので、「せっかくだから、角館〜鷹ノ巣間を秋田内陸縦貫鉄道経由にしてみるか」とも考えました。ただ、当たり前といえば当たり前かもしれませんが、長崎発の乗車券に組み込むことができるような、超広域的な連絡運輸はしていませんでした。 列車が停まる範囲は、きちんとホームの除雪がなされていますが、車両が停車しないような端っこは、もう積もりたい放題です[⑭]。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
 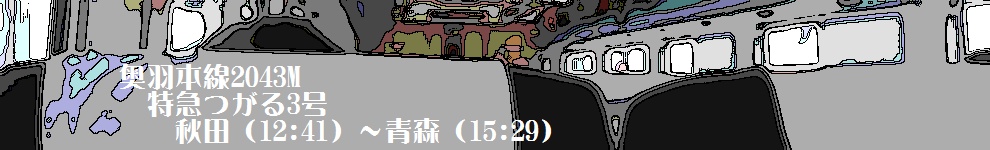 
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
下川沿で運転停車[①]。秋田〜青森間の奥羽本線は、部分的な複線化しか行われていないため、行き違いによる運転停車が発生します。それはまだ良しとしても、同区間の最高速度が95km/hに設定されているのは、とても残念な話です。E751系は、130km/hで走れる性能を持っているというのに、それより35km/hも低い数値にずっと押さえつけられるというのです。 今日の特急つがる3号は、あまり人が乗っていません[②]。まあ、だからこそ、1日に3往復しか運転されていないのでしょうが。2016年3月のダイヤ改正で、5往復→3往復に減便されました。また、一時期、青森〜大館間に、”毎日運転の臨時列車”として、つがる51号〜54号が運転されていたこともありましたが、乗車率は振るわず、これも廃止されています。 白沢〜陣場間を走行中です[③]。同区間には、有名な撮影地があり、あけぼの号や日本海号を撮影するために、多くの鉄道ファンが集いました。が、ただの平日に、ただのつがる号を撮りに来ている人はいるまい・・・。いま、奥羽本線には、今すぐ撮影をするべき車両や列車はないかと思いますが、そのようなものが出てきたときには、また多くの人々で賑わうことでしょう。 津軽湯の沢を通過[④]。築堤上に設けられた小さな駅で、普通列車でも、一部は通過してしまいます。2018年度の冬からは、冬期休業(12月1日〜3月31日)の駅ということになり、見ようによっては、廃駅へのカウントダウンが始まったともいえます。奥羽本線・赤岩や、山田線・大志田、浅岸といった駅も、まず通年→冬期休業という段階を踏んでから、最終的に廃駅になりました。 石川の手前で、弘南鉄道大鰐線の線路が上を跨いでいきます[⑥]。これまで奥羽本線の東側を走っていた同線は、ここで西側に移ります。この路線は、最終的に中央弘前駅に至りますが、同駅は、”弘前駅における弘南鉄道の駅名”ではなく、独立した別の駅です。一方で、”弘前駅”には、弘南鉄道弘南線が乗り入れています。大鰐線と弘南線は接続していません。 弘前に着きました[⑦]。主要な駅ということもあって、下りる人も乗る人も見られます。弘前〜青森間の営業キロは37.4kmで、50kmまでのB特急料金が適用されます。1日に3往復しかありませんが、時間帯が合うならば、気軽に乗っても良いでしょう。新青森で新幹線に乗り継げば、乗継割引が適用されて、つがる号の特急料金は半額にもなります。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
 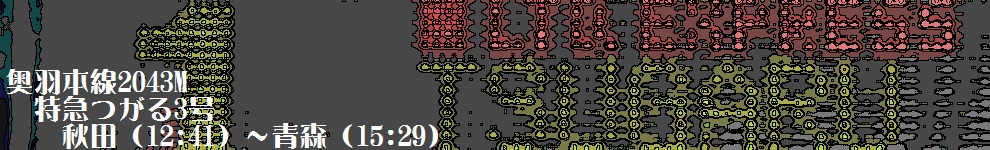 
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
弘前貨物駅構内[①]。1日に1往復のみ、青森信号場との間に貨物列車が設定されているようです。1日に1往復という本数も「うーむ」という感じですが、その運転区間が弘前〜青森間というかなりの短区間であることには、更にびっくりです。それくらいの距離であれば、それこそ「もはやトラックでいいのでは」となりそうですし・・・。 雪雲にびっしりと覆われた空に、地面に降り積もった雪。川の色は黒く、木々は枯れ果てて、なんだか鬱蒼とした雰囲気・・・。私が思い描く「北国の冬」の景色は、大方この車窓のような感じです[②]。このまま白黒写真にしてもほとんど変わらないような、こういったモノトーンな景色は、私にとっては、まさに”冬の景色”と言うべきものであり、「寒いところの来たわけだ・・・」と、しみじみと思います。 川部を通過します[③] [④]。五能線との接続駅ですが、青森方面から(へ)川部で五能線(奥羽本線)に乗り入れると、地域の主要駅である弘前に停車することができなくなります。そのため、リゾートしらかみ号は、一度弘前に立ち寄ります(青森行きは1回目の通過時に川部に停まり、秋田行きは2回目の通過時に停まる)。 人もない、車もない、動物もない、建物もない、もはや植物もない[⑤]。「そこにあるのは、雪と空気だけ」といっても過言ではないような、ちょっとした絶望感すらも覚える眺めです。北国の厳しい冬を体現するような車窓であり、外のその寒さを想像すると、窓を1枚隔てた車内における暖かさとの”差”が、より一層強調されるような感じがあります。 除雪を諦め、冬期は閉鎖となる踏切[⑥]。雪が多く降る路線では、それほど珍しいことではなく、上越線などでも見られます。向こうに見える灰色の一本線は、用水路ではなく、ここを通る道路なのですが、踏切の前が雪捨て場に使われてしまっているようです。雪解けの季節を迎えるまで、この踏切は「冬眠」ということになります。 窓越しの世界では、横殴りの大雪が降っています[⑦]。真冬の2月にこの旅を実施するにあたっては、北日本に行ったときの雪害を、何よりも心配していましたが、この大雪に対して、果たしてつがる号は耐えられるか。こうした大雪に見舞われる中でも、地域の住民の生活を守るために、除雪車は手を休めることなく奮闘します[⑧]。 大釈迦で運転停車[⑨]。また列車交換です。ただでさえ最高速度95km/hに甘んじているのに、列車交換のための運転停車が起こるとなれば、秋田〜青森間185.8kmで2時間48分もかかるわけです(表定速度は66.3km/h)。 津軽新城を通過すると、次は新青森です[⑩] [⑪]。そして列車は新青森に到着[⑫]。この後、北海道に行くために新幹線に乗るので、ここで列車を降りれば、つがる号に乗継割引が適用されるのですが、青森まで乗り通すのでそうもいかず・・・(特急券を新幹線乗り継ぎの新青森までとし、新青森〜青森間は特急券不要の特例で乗っている、と主張するのはアウト)。 青森駅構内に設置された無数の分岐器を、車体を左右に揺らしながら乗り越えていきます[⑬]。青森駅到着直前に感じるこの揺れと音に、私は、「(最果ての)ターミナル駅に着く」という実感を強くします。特に、長距離を走る夜行列車で青森に降り立つときは、より一層その思いに浸ったものです。道中の悪天候にひるむこともなく、列車は定刻で青森に到着しました[⑭]。 |
||||||||||||||
TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |


































