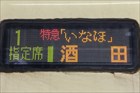Page:99 ※各画像はクリックすると拡大します。 |
||||||||||||||
 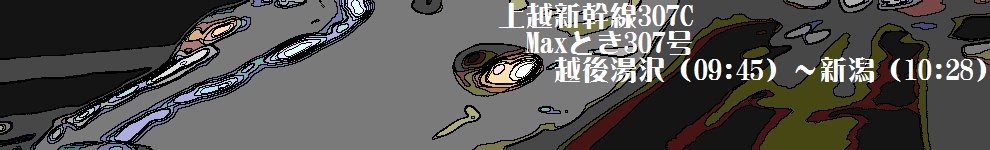 
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
Maxとき307号が到着します[①]。東北新幹線を走っていたころは、E4系やまびこ号は、東京〜福島間において、新在直通のつばさ号を連結することがありました。あれは「新幹線の中でも飛び切り大きな車両と、在来線サイズの車両」という組み合わせでしたが、E4系同士の連結とは、即ち「新幹線の中でも飛び切り大きな車両×2」ということになります[②]。 一面の銀世界となっている湯沢町[③]。このとき、沼田市(標高390m。後閑駅は399m、沼田は後関のひとつ手前の駅)では、積雪は0cmであったのに対し、湯沢町のそれは158cmでした。いかにも雪国らしく、白銀の世界が際限なく広がっていながらも、今日の天気は素晴らしく、雪の白と空の青が、非常に素晴らしい対比を成していました[④]。 浦佐は通過します[⑤]。長岡、燕三条は停車するので、Maxとき307号への乗車中においては、ここが唯一の通過駅です。東京方面から只見線に乗るときは、浦佐で下車すると、上越線に乗り換えて2駅で起点の小出に辿り着けるので、なかなか便利です。そのときは、東京・上野からではなく、大宮から乗車するようにすると、新幹線特急料金も大幅に節約できます。 まもなく長岡です[⑥] [⑦]。長岡は雪がよく降る場所ですが、平年の2月22日の積雪が54cmであるのに対して、2018年2月22日(今日)は、96cmとなっていました。2月8日には、145cmにまで達していましたから、これでも減った方です。長岡に限ったことではありませんが、2017年度(2018年初)の冬は、本当に雪が多く、これには「平成30年豪雪」の名称がつきました。 長岡駅では、消雪用の温水が撒かれていました[⑧]。分岐器など、雪が積もる(詰まる)と問題が生じる場所に温水を撒くことにより、雪害の発生を事前に防いでいます[⑨]。豪雪地帯を通過する新幹線としての知恵と工夫であり、首都圏の在来線等でたまに起こる「分岐器での雪詰まり」は、決して生じることはありません。 越後平野を快走していきます[⑪] [⑫]。その名の通りに水平な土地が広がり、夏は緑も瑞々しい水稲で満ち溢れるこの場所は、冬は、美しい雪原へとその姿を変えます。E4系の2階部分からであれば、それをまさに”堪能”可能。この広大な土地を生かして、上越新幹線の線路は、長岡〜新潟間では、新幹線としてもかなり例外的なほどに直線区間が続きます。 終点の新潟が近づき、都市部へと入りました[⑬]。新潟市は、日本海側で屈指の都市であり、日本海側では唯一の政令指定都市でもあります。果てしなく広がる雪原から一転、”街”に踏み入れた列車は、ほどなくして、終点の新潟に到着しました[⑭]。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
  
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
まさに「壁」という表現が似合う、E4系の巨体[①]。見晴らしの良さをとれば、当然2階席ということになりますが、あらゆるものが超高速で眼前を駆け抜ける1階席も、また異なった魅力があります。一方、勝手知ったる”ツウ”がよく選ぶとされるのは、平屋席。天井が高く、かつ座席数が少ないので、半個室のような感覚があるのです。 このとき、新潟駅では、高架化工事が進行中でした[②]。構造物が完成しているのみならず、ホームドアや案内標示等も整備済みで、モノ自体は、大方出来上がっているように感じられました[③]。とはいえ、高架駅の第1次開業は、この年の4月15日だったので、当時はまだ「未完成」だったのです。いわば、完成寸前の新駅を見ているような気分と申しますか・・・。 高架化によって成し遂げられることのひとつが、「東京〜庄内地方間の所要時間の短縮」でした。高架化と高速化がどう関係あるのか、と思われることでしょうけれども、新幹線の11番線は、在来線のホームにも接するようにされ、そこに特急いなほ号を停車させることで、新幹線といなほ号の対面乗り換えを可能とします[④] [⑤]。まあ、それで何分短縮できるかというと・・・、なのですが。 新潟駅新幹線改札口[⑦]。本当にどうでもいいことなのですが、私は、ここで旅程表を失くしました(笑) ただ、そういった事態もあるだろうという想定はしていて、エクセル版(旅程表は、エクセルで作成しています)をスマートフォンの中に忍ばせてあったので、問題にはなりませんでした。何でも備えあれば患いなし、ということですね。 新潟駅南口駅前[⑧] [⑨]。表玄関は北口なので、こちらは裏手側です。まあ、たしかに、心なしか、人通りや車通りも少ないようには思われます。ところで、”新潟県”と聞くと、それだけつい大雪を思い浮かべてしまいがちですが、新潟は新潟でも、新潟市内(市街)は、それほど多くの雪が降るところではなく、今日この時点の積雪は、6cm程度でした。 新潟駅前のビックカメラで宣伝される、Windows 8搭載のパソコン[⑪]。2015年7月には、その後継となるWindows 10が発売されたので、「この期に及んで、いったいいつのものを・・・」と言いたくなってしまいます。個人の町の電器屋レベルならともかく、大手家電量販店でも、このようなことが起きてしまうことがあるのですね。 南口駅舎[⑫]。一部の人たちの間でたまに話題になるとかならないとかいう、「新潟駅は、メインとなる北口は古びたボロ駅舎なのに、裏口となる南口の方は新しくて綺麗な駅舎だ」という”矛盾”。2023年度中には、万代口広場(北口)の整備が完了し、一連の駅の大改造は、いよいよ終幕を迎えます。そしてそのころには、北口の駅舎も、建て替えが終わっているようです。 新潟駅の高架化工事に際して、4月14日は、大規模な列車運休と代行輸送が行われるとのことでした[⑬]。この中で、多くの鉄道ファンの関心を集めたであろうものは、「特急いなほ号に代わって豊栄〜酒田・秋田間で運転された臨時快速」でしょう。その快速は、いなほ号より多少遅くされたものの、停車駅はそれと同一、車両もE653系だったようです。 10:58発の特急いなほ3号に乗車します[⑭]。「高架化による新幹線といなほ号の対面乗り換え」は、今回の高架化工事における目玉のひとつですから、地上ホームから発車するいなほ号というのは、まさに今が最後です。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
  
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
地上ホーム2番線に停車する特急いなほ号[①]。車両は、かつて我が地元・常磐線を特急フレッシュひたち号として走っていた、E653系です。いなほ号への乗車は、まだ全列車が485系で運転されていた時代の2008年8月に、坂町〜余目間で乗車して以来となります。 いなほ号の運転区間は2種類あり、ひとつは、新潟〜酒田間[②] [③]。もうひとつは、新潟〜秋田間です。定期で運転される7往復のうち、4往復が酒田発着で、3往復が秋田発着となっています。かつては新潟〜青森間を通して走る便もありました。 今回は、このいなほ3号に、終点の酒田まで乗車しますが、ここではグリーン車を選択してみました[④]。E653系いなほ号のグリーン車は、各所から非常に高い評判が上がっていて、「それならば、一度この身をもって確かめてみたい」と思っていたのです。グリーン車、かつ日本海側となるA席は、非常に人気が高く、繁忙期には、その切符の購入難易度は高いとも聞いています[⑤]。 E653系のグリーン車で、まず何よりも高く評価すべきであることは、座席配列が2+1となっていることに尽きます[⑥]。255系以降のJR東日本の特急型車両は、一般用途には供されないE655系を除き、グリーン車は全て2+2配列とされていました。新造車両ではなく改造車両だからなのか(理由になるか?)、それとも新潟支社の権限は強大なのか、ここに2+1のグリーン車が実現しました。 新潟を発車し、列車は北東方向を目指します。阿賀野川は、新潟県を代表する川であり、ここに架かる阿賀野川橋梁は、全長約950mほどの長さを有しています。ゆえに、非常に”渡りごたえ”があるというものです[⑦] 先ほど新幹線で見たものに負けず劣らずの、とても素敵な雪原[⑧]。高架で駆け抜けていた新幹線とは異なり、在来線は地上に線路が敷設されているので、その分だけ視点が低く、また違った眺めになります。ここはまだ新潟市内ですが、御覧の通り、その雪の量は、市街よりもかなり増えていて、最初の停車駅の豊栄では、これくらいになっていました[⑨]。 E653系いなほ号のグリーン車の素晴らしいところ、その2。それは、かつてないほどに広大で余裕のある座席間隔です[⑩]。このグリーン車は、もともとは普通車だった車両の改造で生まれましたが、普通車(910mm)では2列分だったところを、1列で使用しています。つまり、その座席間隔は、脅威の1,820mmにまで達しています。 実際には、各座席の間に仕切り板があるので、前方に1,820mm分の余裕はないのですが、それでも、座席の前にスーツケースとリュックを置いても、それほどキッツキツにはなりません[⑪]。また、この仕切り板があることによって、前の座席の客がいくらリクライニングをしようとも、こちらには何の影響もありません。逆にこちらも、いくらでもリクライニングし放題です[⑫]。 坂町に到着しました[⑬]。新潟からの営業キロは49.3kmで、ぎりぎりで「50kmまでの特急料金」が適用されます。自由席において新幹線との乗継割引を適用させると、510÷2≒250となり、非常に低廉にいなほ号へ乗れます。米坂線と接続する駅でもあり、坂町を発車すると、ほどなくして、東の米坂へ向かって、単線非電化の米坂線が分岐していきます[⑭]。 |
||||||||||||||
TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |