 Page:114 ※各画像はクリックすると拡大します。 |
||||||||||||||
 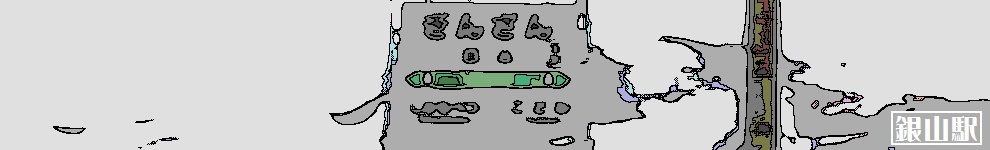 
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
銀山駅で降りました[①]。銀山、という名前にふさわしい、一面の銀世界です[②]。駅の裏手は山になっているので、”銀”世界が”山”をも覆い尽くしているというところです。ホームも雪だらけなので、スーツケースを転がすのも一苦労・・・。 駅名標の裏に積もっている雪を見れば、現在の積雪がどれくらいのものであるのかがよく分かります[③]。先ほど倶知安駅で会話をした例の人によると、「今年の雪は多い」とのことだったので、例年よりも降雪量は多いのでしょう。ホームにある小屋(倉庫?)の屋根は、手つかずの積雪がそのまま残っていて、素人目からすると、建屋が押し潰されるのではないか・・・と心配になります[④]。 駅構内の状況[⑤]。現在は2面2線ですが、1度棒線化され、その後再度2面2線が復活したという、ちょっと変わった歴史を持っています。都市近郊の路線が、列車本数の増加に伴い、交換設備を設けた・・・というのではなく、輸送量も本数も漸減していく地方の路線が、一度なくした交換設備を復活させたというわけです。 駅前の様子[⑥]。見渡す限りの雪、雪、雪。道路の除雪はきちんと行っているようですが、そのために、両側に雪の壁が出来上がっています[⑦]。それは、人の背丈を優に超すようなものであり、まさしく存在感があります。 雪の降りが強くなってきました[⑧]。雨であれば、「なぜ、はるばるこんなところに来て雨に濡れるのか?」と、これほど空しいものも他にないのですが、「冬の北海道における雪」であれば、それは、いかにも北海道に来ていると思わせてくれるものであり、むしろ遠い北の大地を旅しているという気分を高めてくれます。雪質も良いので、案外服も濡れないですからね。 銀山駅は坂を上った先にあり、通りはやや下の方にあります。駅前から坂を下った方面を見ると・・・、雪のせいで視界が悪く、よく見えません[⑨]。建物の影は見えますが、それ以上のものは分からない、というところ。 坂を上ってくると出会えるのが、銀山駅の駅舎です[⑩]。北海道には、車掌車を改造して駅舎として運用している駅もありますが、銀山駅では、小ぶりながらもがっちりとした駅舎が使われています[⑪]。通常は無人駅ですが、冬期ということで除雪部隊が派遣されているのか、駅舎の正面右側に見える事務室の照明が点いています。 駅舎に入れば、どんなに過酷な雪や寒さとも無縁です[⑫]。ベンチやごみ箱も備え付けられていて、列車が来るまでの時間を過ごすには、十分な環境です。除雪用のスコップが準備されているのは、北海道の駅らしい光景と言えます。例え小さな無人駅であっても、除雪はきちんと実施されるので、「あまりの雪で乗り降りできなかった」ということは起こりません。 発車時刻表[⑬]。倶知安行きばかりではありますが、上り方面の本数もそこそこあります。といっても、1〜2時間に1本では、やはり「まともに使える」とは言い難いでしょう。個人的には、1時間に1本が「鉄道として存在する意義」を最低限満たせる水準で、30分に1本が「ギリギリ実用性がある」、15分に1本が「ある程度使える」、自家用車ではなく鉄道を使えというならば、10分に1本は必要でしょう。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
 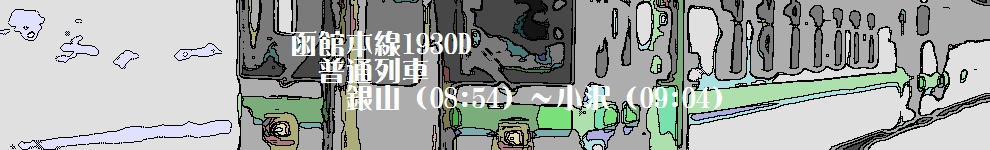 
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
ひとつ手前の小沢に折り返します[①]。「その駅で同じ方面の列車をずっと待ち続けていたら、いたずらな待ち時間が発生する」というときに折り返してみるのは、鉄道ファンの多くが実践する技ですね。これで訪問できる駅もひとつ増えるわけですから、良いことづくめです。 多くの木々は落葉し、枯れ木になっています[②]。その足元は雪が覆っていて、土は見えません。この季節は、冬眠をしている動物も多いはずなので、”生気のない眺め”の感は、より強くなってしまいます。 小沢に着きました[③]。駅間の所要時間10分です。もちろん、あまり飛ばして走っていないということもありますが、9.8kmという長めの駅間距離も、所要時間の長さに繋がっていると言えます[④]。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
  
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
この駅は、いわば「読めそうで読めない駅」と言えるかもしれません[①]。この漢字を見て「こざわ」だと判断する人は、まずいないでしょう。ふつうは「おざわ」ですよね。同じような例のひとつとしては、大船渡線の陸前高田が挙げられるかと思いますが、あれは街の知名度が高いので、案外きちんと読んでくれるかもしれません(りくぜんたか”た”)。 1面2線の小さな駅ですが、かつては岩内線が接続していました[②]。また、特急列車は通過していましたが、急行列車は停まっていました。経てきた年月を感じさせる古びた跨線橋が、ここが主要駅であったことを感じさせてくれます[③]。 ホーム上には、除雪用の機械が置かれていました[④]。細かな部分や凹凸がある部分は、スコップで人力除雪をするのが適当でしょうが、ホームなど、平らで面積が広いところであれば、除雪機を使って一気に排雪することができます。こうした除雪が抜かりなく行われているおかげで、厳寒であっても、利用客は安心して駅を使うことができるのです。 立派な造りをしている跨線橋は、木造と鉄筋のハイブリッド[⑤]。幹になる部分は、鉄で構成されているようですが、壁や屋根は木造になっているようです。使用されている木板はそのままの状態であり、塗装や何かしらの加工は施されておらず、思った以上に「木造」です。 ホームに接続する階段は、一方が閉鎖されていて、片側しか使用できません[⑥]。いま、この駅に発着する普通列車は、基本的に、全てが前乗り・前降りのワンマン列車で、列車の一番前の扉は、上り・下り共に、屋根がある部分(もう一方の階段があるところ)に停車するようになっているため、そちら側の階段さえあれば十分ということなのでしょう。 階段の柱に掲げられた「跨線橋」と書かれた木板[⑧]。うん、まあ、そりゃ跨線橋ですよね。見ての通り。・・・という一言で片づけるのは簡単ですが、意図してか意図せずしてか、「跨」という漢字が、少々妙なことになっています。どう説明すれば良いのか、ちょっと難しいのですが、「飛び出してはいけないところが飛び出して」います。そういう異体字なのでしょうか? 小樽・札幌方面が2番線で、倶知安・函館方面が3番線とされています[⑨]。1番線が欠番となっていますが、この1番線が、かつての岩内線乗り場でした。札幌方面へは、1日に1本だけ、札幌まで直通する快速ニセコライナー号がありますが、函館方面は、最遠でも長万部行きしかないので、「函館方面」と言いつつも、函館まで直通することはできません。 綺麗な状態が保たれている跨線橋内部[⑩]。ボロボロで隙間があれば、中に雪や寒風が吹き込んでくることもあるでしょうから、それがないということは、この跨線橋の状態が悪くないということを示しています。屋根を構成する木材は、長年の歳月によって朽ちてきていますが、”朽ちる”といっても、それは「劣化する」というよりもむしろ、「より味わいを深めている」と解釈できるものです[⑪] [⑫]。 「ようこそ共和町へ 小沢駅職員一同」[⑬]。有人駅時代の名残ですね・・・。 |
||||||||||||||
TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |






























