 ◆2月15日◆ Page:47 ※各画像はクリックすると拡大します。 |
||||||||||||||
 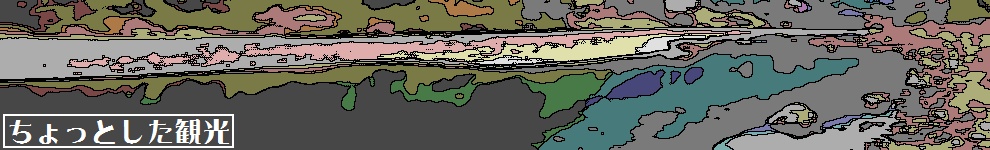 
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
翌朝の朝食[①]。デザートとなるイチゴ以外は、いかにも和食という内容で、普段よく利用するそこらへんのビジネスホテルの洋朝食やバイキングでは、絶対に食べることのないような献立でした。 さて、せっかく江川崎という”中途半端な(ここでは良い意味で使っています)”場所に宿泊したのですから、ただチェックアウトしてそのまま出て行くのは、どこかもったいないです。また、窪川方面行きの列車は、7:15発が初発で、その次は10:50と、前者なら出発が慌ただしく、後者なら遅すぎるという、実に微妙な2つの選択肢しかありません。 そこで、日帰り1500円で利用できるレンタサイクルを使って、ちょっと四万十川沿いをサイクリングしてみることにしました。これでいくらか時間を潰してから、10:50発の列車に乗っていくこととしましょう。 江川崎駅で自転車を借りてやってきたこの場所はいったい・・・?[②] せっかく自転車を借りて四万十川沿いを走るのだとなれば、是非訪れてみたいところがありました。そう、欄干が一切ないとてもスリリングな橋、沈下橋です[③]。四国、それも四万十地方を訪れる機会に恵まれたとなれば、ここを無視していきたくはありませんでした。 今回訪れたのは、駅から最も近いところにある、長生沈下橋です[④]。もっとも、近いとは言っても、3.2kmの距離があって、自転車といえども、訪れるのは意外と楽ではありませんが。車同士のすれ違いは絶対に不可能という程度の幅に、部分的な補修がいくつもなされた表面。靴くらいは引っかかりそうだ、という程度の高さの柵すらもなく、まさに車道だけが真っ直ぐに伸びています[⑤]。 と、そのとき、1台の軽自動車が長生沈下橋を通行していきました[⑥]。この橋は、何も歩行者専用というわけではないので、自動車も当たり前のように横断します。とはいえ、走り慣れた地元の人でなければ、とても通行は推奨できないでしょうけれども・・・。ただ、いち観光客としては、車を借りてここを渡ってみるというのは、是非ともやってみたいですがね。 普通の透明とはまた違う、どちらかというと「緑色」に見える川面は穏やかで、周囲にある山の稜線を上下反転にして映しています[⑦]。雲はだいぶ低い位置にまで降りてきていて、手近な山の山頂よりも下のところに来ています[⑧]。まるで水墨画に出てきそうな、ちょっと不思議で、ちょっと神秘的なこの雰囲気は、私にいかにも”旅をしている”という気分を作ってくれます。 だいたい、沈下橋というのは、「川が荒れ狂ったときに、流れてきたゴミや流木が欄干に引っかかり、水の抵抗が大きくなって橋が損壊することがないように」ということでこのような作りをしているわけですが、今の四万十川は非常に穏やかで、水位も橋脚の全体が見えるほどに低いです[⑩]。それはまさに清流としての佇まいで、これが荒れた姿は想像もできません。 沈下橋から更に1.5kmほど奥の方へ走ってきました(対岸には行っていません)[⑪] [⑫]。本当は、いくつもいくつも沈下橋を巡ってみたい(それぞれで造りが異なっています)ところなのですが、それだけの時間はないので、ある駅を訪れてお茶を濁します。それは、半家駅です[⑬]。「←半家駅」と記された標識の先にあるのは、民家の軒先と階段・・・[⑭]。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
  
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
築堤の上に設けられている半家駅。予土線は、誰の目にも明らかなローカル線ですが、ここで枕木にPC枕木が使用されていることに気が付いた方は鋭いですね[①]。半家を含む江川崎〜若井間は、1974年3月になって開業した新しい区間であり、その結果、PC枕木の採用やトンネルの多用による(比較的)直線的な線形など、北宇和島〜江川崎間よりも高規格です。 半家駅の構造は、1面1線[②]。そうじめじめとした時期でもありませんが、ホームには苔が生えています。その駅名から、散々ネタにされがちな半家駅ですが、まかり間違っても「ハゲ駅」ではなく、漢字で「半家駅」です[③]。半家〜増毛間の乗車券を買うことが、一部の界隈で流行っていたようですが、留萌本線の一部区間の廃止により、それも今はできなくなりました。 普段は清流と呼ばれる四万十川も、時には暴れ川に早変わりします。また、予土線の江川崎以東の沿線は、基本的に山がちであり、山崩れや土砂崩れに遭う危険性も孕んでいます。そういったこともあってか、駅には、災害時の避難場所と代行バスの停車場所が示されていました[⑤]。当たり前といえばそうですが、なにぶん築堤の上にある駅なので、バスは下の道路に停まります。 座面と背もたれの比率が明らかにおかしい長椅子・・・[⑥]。あまりきれいではなかったので、実際には座っていませんが、見る限り、座り心地の良さそうなものとはとても思えません。椅子本体は、全面的に緑色に塗装されていますが、もしかしたら、「しまんとグリーンライン」にかけているのかも。 先ほども触れたように、半家駅は、築堤上にホームが置かれている駅であり、道路との行き来には階段を使用する必要があります[⑧]。もちろん、このような無人駅にエスカレーターやエレベーターがあるはずもないので、バリアフリーの概念とは真っ向から対立しています。もっと言えば、予土線の車両(キハ32形)も、ステップ付きの車両なので、バリアフリーとは言い難いです。 独特の雰囲気と川面の色をもって、一般的な川にはないような神秘的な空間を作り出す四万十川[⑨] [⑩]。水深の違いが、そのまま水の色の違いとなって表れており、浅いところは透明に近い色合いで、深いところは緑とも青ともつかない不思議な色合いをしています。浅い〜深いにかけてのところに現れる諧調は、これまた美しいもので、まさに芸術的な光景です。 江川崎駅で自転車を返却し、予土線の列車に乗車します[⑪]。「おや」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、左側通行が基本となる日本では、鉄道もまたそれに倣っており、島式ホームをレール方向に眺めると、右側に”手前に来る列車”、左側に”奥に行く列車”が停車することが普通です。ただ、江川崎駅では、なぜかそれが入れ替わった状態で上下の列車が行き違います[⑫]。 宇和島行きの普通列車は、昨日乗車した0系風の車両でした[⑬]。しかし、私は窪川方面へ進むので、乗るのはこちらではありません。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
 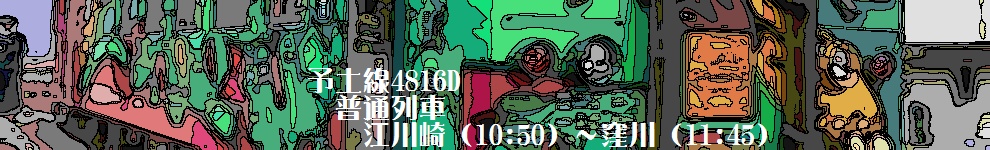 
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
0系風のキハ32形もなかなかに強烈ですが、こちらも相当な色物です[①]。「かっぱうようよ号」と名付けられたこの車両は、外も中も河童であふれています。2011年より運行を開始していて(意外と歴史は長いのです)、現在のこの車両で3代目(新しい車両に取り換えられているのではなく、デザインが変更されている)となります。 昨日の0系風車両ではプラレールが展示されていた場所に、このかっぱうようよ号では、河童にまつわるジオラマないしはフィギュアが展示されています[②] [③] [④]。どちらもプラレールとは異なり、割とリアリティがあると言いますか、そこまで子供向けにデフォルメしてはいないので、河童といっても、アニメ調の「愛らしさ」はあまりありません・・・。 ロングシートの一角に、河童が座っています[⑤]。見てのように、のど元にはスピーカーがついていて、人が通ると喋ります。団体で賑わっているときならともかく、今日はそうでもなかったので、静かな車内で河童がひとりでに喋る様は、ある意味不気味。 江川崎を出ると、すぐに広見川を渡ります(四万十川ではないことに注意!)[⑥]。そしてトンネルを1本抜けると、列車はしばらく四万十川沿いに走り続けます[⑦]。全通が遅く、川沿いに走り続けるローカル線という点において、2018年3月をもって廃線となった三江線によく似ています。そして、存廃の危機的状況にあるという点においても、また・・・。 先ほど自転車で訪れた、長生沈下橋が見えました[⑧]。そして、続いて半家駅[⑨]。今朝自転車で走ってきたのは、予土線の線路沿い(と、四万十川沿い)を走る国道381号線だったので、ここまでの景色はおおむね知っています。自転車で走れる距離には限りがありますが、車ならどうとでもなるので、そのうち四万十川沿いのドライブなどもしてみたいものです。 江川崎〜若井間は、1974年に開通した比較的新しい区間ということで、全体的には高規格です。そのため、川沿いをくねくねと走るのではなく、トンネルと橋梁で川を横断する個所も数多くあります。「第6四万十川橋梁」ということは、少なくとも6つは、このように四万十川を渡る橋梁があるということですね[⑩]。実際のところ、第何まであるのでしょうか? 特に名前はついていなさそうですが、もう一丁四万十川を渡ります[⑪]。保守作業員が退避地帯に立っていますが、トラス橋ではなく、線路そのものしかない種類の橋梁で、そのうえ眼下には四万十川が待ち構えているので、結構スリリングな状況に見えます。コンクリート造りの高架橋でもないので、隙間も多いですしね・・・。 「四万十川」から「四万」を抜いた十川駅[⑫]。本当の由来が知りたいところです。ちなみに、この次の駅は土佐昭和で、更にその次が土佐大正と続ています(土佐平成と土佐明治はありませんが、いっそのこと、”観光資源づくり”のために、そのように改名するのもアリでは)。 |
||||||||||||||
TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |








































