 Page:69 ※各画像はクリックすると拡大します。 |
|||||||||||||
  
|
|||||||||||||

|
|||||||||||||
回送表示の521系[①]。北陸地方だけで運用されている車両であり、地域性が高いので、私にとっては、北陸地方に来たことを実感させてくれる車両のひとつです。湖西線では、南は近江今津まで乗り入れています。 敦賀を発車すると、ほどなくして、全長約14kmの北陸トンネルに入ります。在来線としてはかなり長い部類に入るこのトンネルを抜けるには、当然、長い時間がかかりますが、ようやくその終わりが見えてきました[②]。ずっと暗闇が続き、目も暗い場所に慣れてきたであろうかという頃合いに・・・、サンダーバード7号は、北陸トンネルを脱出しました[③]。 湖西線を走っていたときから、「段々と雪が増えてきたな」と思っていましたが、北陸トンネルを抜けた先に待ち構えていた銀世界は、まさに豪雪に見舞われた後のそれでした[④]。雪の量は、敦賀までの区間とは比べ物にならないほどに多く、しかしそれでいながら青空が見えるという天気の良さが、台風一過ならぬ豪雪一過の穏やかな雰囲気を、より一層強めていました[⑤]。 上りのサンダーバード号とのすれ違い[⑦]。北陸新幹線が金沢まで達する以前は、サンダーバード号、しらさぎ号、はくたか号、北越号、寝台特急・・・など、多くの特急列車が頻繁に行き交い、北陸本線(とりわけ金沢〜富山)は、特急街道とも呼ばれました。もちろん、今でも、敦賀〜金沢間は、多くのサンダーバード号・しらさぎ号が高頻度で運転されています。 武生に停車[⑧]。奥に見えているモーターカーは、ここ数日の大雪において、大いに活躍したことでしょう。モーターカーを運用する場合は、他の列車が入線できなくなる措置・・・、線路閉鎖を取る必要があり、普通の営業列車と同時に使用することができないのですが、あれほどの大雪となれば、そのようなことは問題にならなかったでしょうね。 武生駅発車後の車窓[⑨]。駐車場に停められている車の大きさと、その背後に見える雪山の大きさを比較してみれば、今回の大雪が、いかに異常なものであったのかがよく分かります。いかに除雪した雪をかき集めたものとはいえ、あんな高さになるとは・・・。 越前花堂〜福井間にある、南福井駅。JR貨物の貨物駅ですが、JR西日本の旅客列車を留置する場としても使用されています[⑩]。福井という地が、雪が降る場所か降らない場所かでいえば、それはもちろん前者なのですが、とはいえ・・・。この2018年、福井では、最大147cmの積雪量となったほか、武生でも130cmの数値を記録しました。 福井でサンダーバード7号を下車します[⑪]。先ほど堅田駅で、今日のサンダーバード7号には683系更新編成が充当されていると言及しましたが、大阪方に連結されている付属編成は、まだ体質改善がなされていない681系でした[⑫]。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
  
|
|||||||||||||

|
|||||||||||||
福井駅にやってきました[①]。ひとつ手前の越前花堂は、越美北線が分岐する駅です。よって、本当に厳密に言ってしまえば、福井は北陸本線のみの駅ということになります。もっとも、あと少しで北陸新幹線が敦賀まで開業すれば、福井は、JRの在来線が存在しない駅となってしまうのですが(北陸本線が経営分離されるため)。 高架となっている福井駅[②]。サンダーバード7号に接続する金沢行きの普通列車が、発車のときを待っています。福井を発着する普通列車は、現在、その全てが521系となっているほか、越美北線へ(から)直通する列車はキハ120形、特急列車は681系・683系で運転されるということで、福井は、いつの間にか、JR世代の車両しか発着しない先進的な駅になりました。 北陸本線は、例の凄まじい豪雪から立ち直り、全線での運転が再開されていました。しかし、越美北線についてはそうも行かず、「本日は運休」、「明日は運休」どころか、少なくとも2月21日までの運休が決定していました[④]。復旧の優先度が低いということはあるにせよ、ある程度の期間を持って運休が決まるということは、いったいどれほどの雪が降ったというのでしょうか。 寒いといえば寒いが、寒冷地と呼びたいほどではない。というのが、福井の気候面に対する、私の勝手な印象なのですが、駅舎と外の出入り口には、自動扉が設けられていました(開け放しではなかった)[⑤]。時間がなかったので調べていませんが、福井くらいにまで来ると、コンビニの出入り口も二重扉になっているのでしょうか? 福井駅前[⑥]。う〜ん、雪が多いですね。都市のど真ん中なので、歩道や路上については、当然除雪が行き届いているわけですが、随所で見られる溜まりに溜まった雪が、その大雪の度合いを物語っています。 と、ここで雪がちらつき始めました[⑦] [⑧]。列車の運行に影響が出ることはありませんが、これが思いっきり強烈になってしまった結果が、あの大雪だったわけです。いかにも雪が降ってきそうというような、あの薄暗い感じではなかった(薄日も差していたので)のでが、雪が降っています。まあ、雪国ではよくあることですが。 福井駅、西口駅前の様子[⑧] [⑨]。路面電車は、ひとつ隣の通りを経由しているので、この大通りの写真に出てきません。そんな大通りのとある信号付近にあった、「みどりのスコップひとかき運動」[⑩]。まあ、要は、信号待ち中に雪かきをしておいてくれということなのですが、どれだけの人が協力してくれるのやら。 福井駅駅舎[⑪] [⑫]。ところどころに見られる、突き出したガラス張りの構造部が目に留まります。現在、福井駅では、北陸新幹線の開業に向けた建設工事が進められていますが、新幹線の構造物は、反対側の東口に造られるので、西口にいると、新幹線関連の工事が進んでいることは感じ取れません(建設途中の橋脚等もありませんしね)。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
 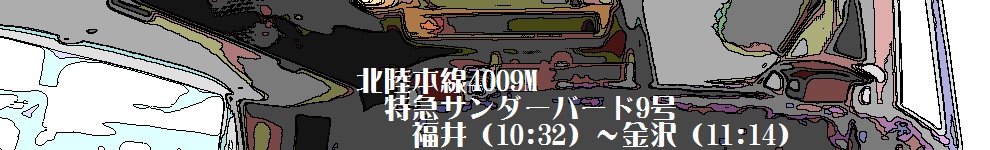 
|
|||||||||||||

|
|||||||||||||
福井から10:32発のサンダーバード9号に乗車しました。余裕綽々で駅前を散策していたら、気が付けば列車の発車時刻が迫っていて、最終的には、かなりの急ぎ足でホームに向かいました。おかげで、発車標の写真を撮ることができなければ、到着する列車の様子を撮ることもできず・・・。なお、7号と9号は、大阪発は30分差ですが、停車駅の違いにより、福井発は19分差となっています。 サンダーバード7号では普通車指定席に乗車しましたが、今回の9号ではグリーン車を選びました[①]。福井〜金沢間の営業キロは75.7kmであり、最安となる100kmまでのグリーン料金区分が適用されるためです(普通車指定席に対し+760円で乗れる)。棚に乗っている荷物の量からも分かるように、今日のグリーン車の乗車率はやや高めでした[②]。 青空が広がる北陸地方を駆け抜けていきます[③]。地面を見てみると、手前から奥まで、本当に切れ目なく雪原が広がっていて、どこにも草木の緑や土の茶色がありません。そして、人間はもちろんのこと、動物の足跡すらもありません。これぞまさに銀世界と言わんばかりの光景です。その白のおかげで、空の青もより一層引き立つというものです。 近頃、全国的にグリーン車サービスの縮小が進められていて、座席が大きいこと(一部の会社を除く!)以外には、グリーン車の取り柄もない・・・というのが実情となりつつありますが、サンダーバード号では、何やらグリーン車の乗客限定のサービスが行われているようです[④]。やっぱり、ハードが良いだけでなく、ソフトでも何かのプラスアルファがあってほしいですよね。 一部の特急列車も停車する大聖寺を通過[⑤]。なんだか、雲行きが怪しくなってきたような気もしますが・・・。北陸新幹線は、現在北陸本線の沿線各所で鋭意建設工事が進められていて、大聖寺〜加賀温泉間でも、設置途中の高架橋の橋脚が見られました[⑥]。なお、加賀温泉には、新幹線の駅が設けられる予定です。 加賀温泉を通過します[⑦]。加賀温泉は主要な駅であり、ほとんどの特急列車が停車しますが、サンダーバード9号では通過駅とされています。それどころか、この9号は、全ての同列車の中でも最も停車駅が少ない最速達型であり、大阪〜金沢間において、途中新大阪・京都・福井にしか停まりません。なお、1つ前の7号は、逆に停車型であり、堅田、近江今津、松任などにも停まります。 気が付けば、窓の外は吹雪となっていて、視界が奪われてしまいました[⑧]。走る場所は線路が勝手に決めてくれるので、自動車ほどには問題にならないのでしょうが、とはいえこの視界で列車を操る運転士は、本当にご苦労な話だと思います。 コマツの企業城下町、小松を通過します[⑨]。福井を出ると、終点の金沢まで一切停車しないので、小松ですらも通過駅です。芦原温泉や加賀温泉よりも重要度は高いと思うのですが、小松を通過するサンダーバード号は少なくなく、別に7号ならではの特別なものというわけではありません。新幹線も、もしかしたらはくたか号しか停まらないかもしれませんね。 北陸新幹線の総合車両基地として機能する、白山総合車両所[⑩]。現在は、新幹線が金沢止まりなので、ここに至るまでの線路は、単なる回送線としてのみ機能していますが、その延伸が果たされたときは、本線に組み込まれることになっています。いわゆる博多南線も、同じような処遇となりましたね(九州新幹線の本線に転用)。 終点の金沢に到着しました[⑪]。こうして貫通型車両(準備工事)が金沢方の先頭に立っているということは・・・、これは683系4000番代だったということですね。4000番代は、2009年以降に製造された車両で、経年は浅い方ですが、これも更新工事の対象となっています。鳥が駆けるこの新しいロゴは、工事施工完了車の目印のひとつです[⑫]。 |
|||||||||||||
TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |




































