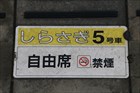Page:73 ※各画像はクリックすると拡大します。 |
|||||||||||
  
|
|||||||||||

|
|||||||||||
下呂まで来て、雪の量はかなり減りました。もちろん、あることにはあるのですが、「融け残りの残雪」といったような具合で、”積もっている”と形容できるようなものではありません[①]。この先の白川口〜上麻生間で、線路は高山本線の名車窓・飛水峡の脇を通過しますが、その手前でも、大自然が形成した美しい眺めが展開されます(雪がないので、全体の様子がよく分かります)[②]。 焼石〜飛騨金山間で、進行方向左手に、古びた吊り橋が現れます[③]。後からストリートビューや衛星写真で追跡してみましたが、この橋の名前は分からず、また、現在は通行止めとなっているようでした。地図上では、そもそも橋扱いされていない(Google Mapでは、この橋は表示されていない)ようでもありますが・・・、詳しい情報をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。 飛騨川の眺め[④]。今回の旅でも乗車した、JR西日本の三江線やJR四国の予土線は、多くの区間で大河(江の川・四万十川)に沿って走りますが、高山本線でも、猪谷〜美濃太田間は、そのほとんどで川沿いを通ります(神通川・宮川・飛騨川)。夏に乗っても、冬に乗っても、高山本線沿線が織り成す車窓は、必ずや旅人を楽しませてくれることでしょう。 太多線の線路と合流すると、列車はまもなく美濃太田に着きます[⑤]。このあたりまでやってくると、段々と岐阜・名古屋に近づいてきたという実感が湧いてきますね[⑥]。そして、窓越しに見える景色からは、とうとう雪は消え失せてしまい、また平地や住宅が増えてきました[⑦]。運転速度も110km/hに向上し、走りの力強さも大きくなりました。 富山からの長い道のりを終えて、列車はようやく岐阜に到着しました[⑧]。下り列車の遅れの絡みがあって、定刻より8分ほど遅れての岐阜到着となりました。列車の終点は名古屋ですが、名古屋まで乗り通すわけにはいかないので、ここで降ります[⑨]。ただし、特急券は名古屋まで購入し、乗継割引を適用させています(その方が岐阜で切るより安いので)。 名古屋に向かって岐阜を発つひだ14号[⑩]。列車はここで進行方向を変えています。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| ↓ | |||||||||||
|
|
|||||||||||
 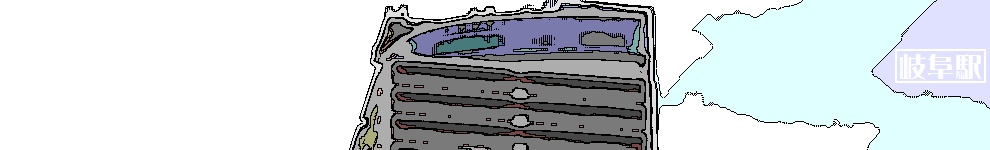 
|
|||||||||||

|
|||||||||||
岐阜駅にやってきました[①]。東海道新幹線に乗っていると、岐阜駅を通過することはなく、県内唯一の新幹線駅である岐阜羽島は、JRの在来線は接続していないため、あまりその存在を意識することはありません(失礼な話ではありますが・・・)。全面的に高架化されている岐阜駅は、東海道本線と高山本線が接続していて、駅構造は3面6線となっています[②]。 17:15発の飛騨金山行きという列車があるようです[③]。これは珍しい行き先だな、と思いましたが、実際、高山本線の列車で飛騨金山発着となっているのは、1日に1往復しかありません。 夕刻が迫る岐阜市街[⑤] [⑥]。2月7日に旅を始めて以来、12日目を迎えた今日は、草津駅から1日が始まりましたが、草津〜岐阜間の営業キロは95.1kmであり、まっすぐ行けば、途中下車すらできないような距離です。そこを520.4kmもの道のりをかけてやってきました。夕方になってようやく目にできた、この岐阜の街並み。ちょっと感慨深いものがあります。 駅のペデストリアンデッキには、冷水器があります[⑦]。「岐阜のおいしい水」と銘打たれたこの冷水器では、長良川を水源とした水道水が飲めるとのこと。飛騨川ではないのですね。 ところで、そういえば、列車内の冷水器って、もう見かけられなくなりましたね・・・。JR線で最後まで冷水器を搭載していたのは、寝台特急あけぼの号用の24系が最後ではないかと思います(北斗星号では見た覚えがない)。 駅周辺には、数多くのビル群が立ち並んでいますが、その中でもひときわ目立つのが、このビルです[⑨]。岐阜シティ・タワー43という名前がついているこのビルは、文字通りの43階建て、高さ162.82mの高層建築であり、もちろん、県内で最も高い建物です。43階部分には無料の展望室があり、そこからは、岐阜市街を一望することができます。私も、2016年3月のとある旅で、ここを訪れています。 県内一のターミナル駅として、外観からその存在感を放つ岐阜駅[⑩] [⑪]。細かな理屈ではなく、単純に”気持ち”として、我が街の玄関口となるべきところは、やはり立派なものであってほしい、というのは、人間の普遍的な思いです。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| ↓ | |||||||||||
|
|
|||||||||||
 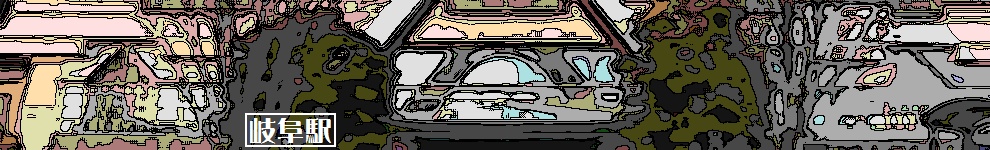 
|
|||||||||||

|
|||||||||||
岐阜駅には、南北の出口があります。北口が市街地側で、南口が住宅地側です。南口は、さすがに北口ほどには賑わってはおらず、いわゆる「閑静な住宅街」への入り口といった雰囲気です[①]。将来、ターミナル駅の近くに住居を構えるのであれば、「裏口」側に住むのが良いかもしれません(利便性と静粛性を両立?)[②]。 17:26発の特急しらさぎ12号に乗車します[④]。岐阜〜名古屋間は、快速系の列車に乗れば、20分で辿り着けるような区間なので、ここでわざわざ特急に乗る人は、あまり多くはないでしょう。ただ、もう何度も言っていますが、「快適性の追求」と「周囲への配慮」のために、私は750円を支払ってここで特急列車に乗車します。 岐阜県には、地方新聞として岐阜新聞社があるようです[⑤]。しかし、その購読率は30%にも達しない程度であり、はっきり言って、存在感があるとは言い難いです。それはなぜかと言えば、中京圏には、中日新聞という非常に強大なブロック紙があるから。 5号車の乗車口で特急しらさぎ12号を待ちます[⑥]。乗車時間は23分であり、さすがに指定席を確保するほどのものではありません。ましてや、グリーン車に乗るなどというのは、もったいないことこの上ないです。まあ、そこらへんの話をし出すと、「そもそも、岐阜〜名古屋間で特急に乗ること自体が、非常にもったいない行為なのでは」という痛い指摘を食らう羽目になりますが。 岐阜駅のホームには、快速ムーンライトながら号の乗車口案内もあります[⑦]。年々運転日数を減らし、185系の引退も迫っているという状況にあっては、この列車の存続を危ぶむ声が出ているのも、致し方ないところではあります。E257系でも運転が継続され、グリーン車も営業するというようなことがあれば、私もまた乗ってみてもいいかなと思いますが、普通車の座席夜行は、もはや私には・・・。 |
|||||||||||
TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |