 ◆2月17日◆ Page:62 ※各画像はクリックすると拡大します。 |
||||||||||||||
  
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
2月17日、土曜日です。昨晩にNHKのデータ放送で見た天気予報では、今日の和歌山県の最高気温は9度で、さらには最大で風速10m/sの風が吹くとも予想されていました[①]。和歌山としては少々肌寒くなりそうです。 「東口本駅舎の早期実現」を願う立て看板[②]。まあ、たしかに、これでは若干みすぼらしい感があるのは事実ですが[③]、自動券売機も、みどりの窓口も、自動改札機も、発車標もすべて完備しているので、「西口と比べると、機能的に格段に劣る」わけではありません[④]。立派な駅舎かどうかというのは、あくまでも見栄の問題だと思います。 東口駅舎の中にあった、三井住友銀行のATM[⑤]。メガバンクは、全ての都道府県で3行ともあるわけではなく(みずほ銀行は全都道府県にあり)、ところによっては、三井住友銀行または三菱UFJ銀行の店舗がない、あるいはその両方がないこともあります。和歌山県については、人口が100万人を切っていて、商業規模的には小さいと思うのですが、3行いずれもが店舗を置いています。 今日は紀伊半島をぐるっと回っていく日です。特急くろしお1号に乗り、紀伊勝浦を目指します[⑥]。ちなみに、なぜ新宮ではなく紀伊勝浦なのかというと、紀伊勝浦までにすると、営業キロが200kmを切り、料金を節約できるからです(その後、南紀号で津へ行きますが、紀伊勝浦〜津と新宮〜津の料金区分は同じ)。 各ホームへ繋がる地下通路に行くと、一番最初に現れる乗り場は、JR線ではなく、和歌山電鐵の9番線です[⑦]。階段を上った先に和歌山電鐵の窓口があり、切符はそこで購入します。そのため、和歌山電鐵に乗るときは、JR西日本の出札窓口でその旨を伝えることで、何も持たない状態でJRの改札口を抜けることができます。 和歌山線のホームに、105系が停車しています[⑨]。側面だけを見ると、103系に見えなくもないですね。103系に実在していた色の塗装であったなら、なおさらそう思えたことでしょう。戸袋窓にグローブ型の通風器など、今時の車両ではあまり見られないような、古めかしい要素も満載です。227系1000番代による置き換えが始まっているので、記録と乗車はお早めに[⑩]。 1号車の乗車口で列車を待ちます[⑪]。それにしても、このくろしお号の乗車位置案内は、なんだかやたらとでかいです・・・。くろしお号に充当される3種類の車両(283系、287系、289系)は、いずれも同じ位置で停車するので[⑫]、扉位置の微妙なズレをカバーするために、これだけの大きさにしているのかもしれませんね(「この”あたり”でお待ちください」という曖昧な書き方にもなっていますし)。 これからやってくるくろしお1号を、和歌山駅の社員が横断幕を持って出迎えます[⑭]。別にデスティネーションキャンペーンをやっている期間ではありませんでしたが、このようなことが行われていました。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
 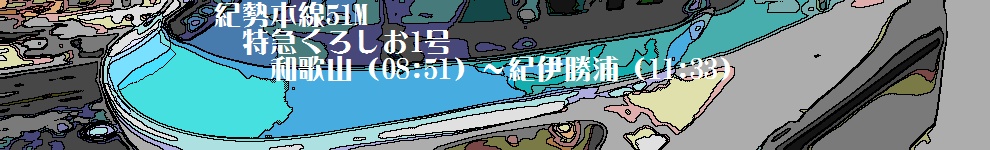 
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
くろしお1号がやってきました[①]。車両は283系です。以前は「オーシャンアロー」を独占的に名乗っていたこの車両ですが、紀勢本線の電車特急の愛称は、「くろしお」に統一されました。ただし、「パノラマ型グリーン車連結」の注記がつくことによって、時刻表上で283系が充当される列車を見つけることは容易です。 今回はグリーン車に乗車します[②]。1番席は確保できませんでしたが、まあ、いいでしょう。新宮方面行きの列車で1番席を確保することができれば、運転室越しに展開する迫力のある眺めを楽しむことができます[③]。 紀三井寺を通過すると、ほどなくして、進行方向左側に、その名の通り「紀三井寺」が現れます[④]。私は、このお寺については全く知らなかったのですが、観光地としてそれなりに名を馳せているということなのか、車掌から、紀三井寺についての観光案内の放送も入りました。見えるのはほんの一瞬だけなので、紀三井寺を通過したら、左側の車窓にご注目ください。 海南に到着[⑤]。和歌山市のベッドタウンとしても発展していて、1日に1本だけではありますが、海南始発のくろしお号もあります(新大阪行きの6号)。そして海南を出ると、徐々に海沿いの区間も走るようになり、進行方向右側(D席)を確保した意味が出てきます[⑥]。 紀伊田辺までは複線化されているため、走行中に反対側の列車とすれ違うこともあります[⑦]。和歌山〜御坊間の普通列車は、基本的に223系・225系・227系のみで運転されているため、むしろ国鉄型車両とすれ違う方が難しいと言えます。特急列車も全てJR世代の車両になりましたし、今や、JR西日本でも有数の新型車両率を誇る区間のようです。 藤並を通過します[⑧]。以前は、特急列車は全く停まらない駅でしたが、2008年に橋上駅舎化されたのを機に、一部の特急列車が停まるようになり、また、みどりの窓口も設置されました(2019年3月で営業終了)。普通列車のみの停車から昇格し、近隣の駅が軒並み利用者を減らしていく中でも、しぶとく”現状維持”くらいを保ち続けている、なかなか達者な駅です。 由良風力発電所[⑨]。海南を通過し、海景色が現れたので、「いよいよオーシャンビュー祭りか」と思ったのですが、ところがどっこい、海南から、南部の2つ手前の切目あたりまでは、むしろ内陸部を走り、海はほとんど見られません。 紀州鉄道と接続する御坊に到着[⑩]。JR紀勢本線の御坊駅は、市街地からは離れたところに位置していて、御坊市の街中へは、紀州鉄道が導いてくれます。もっとも、その利用客数は・・・ですが。 再び海が現れました[⑪]。小さな離島はおろか、突き出して顔をのぞかせる岩すらないというようなその光景は、まさに「大海原」で、美しき水平線を邪魔するものはありません。この先には本当に何もなく、四国も方角がちょっと違います。 9:58、紀伊田辺に到着[⑫]。列車運行上の重要な駅で、全ての特急列車が停車するのはもちろんのこと、普通列車についても、1日に1本だけある周参見発和歌山行きを除いては、いずれも紀伊田辺を始終着駅としています。そして線路も、ここまではずっと複線で来ていたのが、紀伊田辺からは単線となり、輸送力も格段に落ちて、一気にローカル線感が強くなります[⑬]。 白浜では、まあ観光客がガンガン降りること[⑭]。それも、日本人ではなく、例によって中国人が大半を占めているような気がしましたが。半数以上のくろしお号が白浜止まりであるように、紀勢本線の特急列車の需要は、白浜までが大勢を占めているため、白浜〜新宮間では、特急も空席が目立つようになります。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
 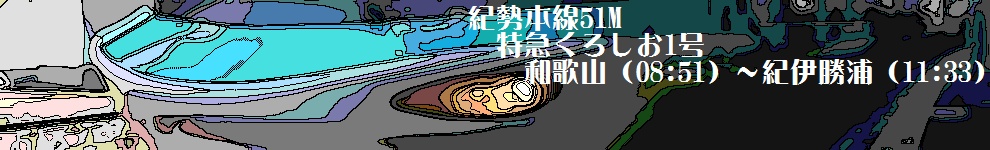 
|
||||||||||||||

|
||||||||||||||
パノラマ型グリーン車となる1号車[①]。イルカを思わせるような形状をしていて、かつて名乗っていたキャッチフレーズは、「海と太陽が大好きな列車」。このような顔を持つ先頭車両がある一方で、普通車の先頭型車両は、いずれも貫通扉を備えていて、増解結運用をこなすことができる実用性も持った車両です。 「白浜から先は、特急の需要も格段に落ちる」ということで、そこそこの乗車があったグリーン車も、空席が目立つようになりました[②]。なお、ご覧の通り、グリーン車は2+1の配列ですが、それが途中で逆転しています。これは振り子を作動させる際に、車両の重心が不均衡にならないようにするための措置です(最初から最後まで2+1だと、左右の重量バランスが良くない)。 白浜の次の駅、紀伊富田で特急くろしお14号と行き違い[③]。283系は、基本編成6両×2本、付属編成3両×2本の合計18両しか製造されなかった小所帯の車両であり、また、付属編成が単独で営業運転に就くことも、通常は行われていないことから、実質的には2本しか稼働しません。その小所帯ゆえ、381系の置き換え完了には、時間がかかったわけですね。 椿を通過[④]。現在は普通列車しか停車しませんが、かつては1日に1往復のみ、特急列車が停まっていました。2011年8月に、わざわざその片道1本しか椿に停まらない特急列車に乗り、ここで降りたことがあるため、そのような意味では、ちょっと思い出深い駅でもあります。ただ、普通列車に乗り換えてまで再度行くか、と問われると・・・。 暇を持て余してきたので、なんとなく3号車のラウンジに行ってみました[⑥] [⑦]。新大阪〜新宮間を乗り通すと、4時間以上の所要時間がかかるため、このような息抜きできる場所があるのは、良いことと言えます。もっとも、グリーン車の乗客は、あまりここには来ないものと思いますが。なお、座席は、全て海側を向いて配置されていて、列車の性格がよく現れています[⑧]。 港を見たかと思えば[⑨]、枝や葉が車体にこすれる音が聞こえるような地帯を走ることも[⑩]。たしかなことは、どう考えても、高速で駆け抜けることができる場所であるとは言えない、ということです。振り子機構を備えた283系といえども、その走りはかなりトロくなってしまい、くろしお1号の白浜〜新宮間の表定速度は、約58.8km/hに留まります。 おっと、今度はトンネルですか・・・[⑫]。せっかく綺麗な海が見える区間なのだから、それを邪魔しないでくれ、とでも言いたくなりますが、こうして”メリハリ”があるからこそ、海景色の価値も高まるのかもしれませんね[⑬]。 本州最南端の地、串本に到着[⑭]。”本州最南端”という響きは、私を魅了するものがあるので、そのうち降りてみたいと思っています。 |
||||||||||||||
TOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DISCOVER どこかのトップへ 66.7‰のトップへ |









































